多様性が叫ばれ「個」が重視される時代、企業の人材育成において画一的な教育のみを実践していては、大きな成果を得られなくなっています。
そこで注目を集めているのが、個々の従業員に向けたカリキュラムをカスタマイズできる、LXPというプラットフォームです。この記事ではLXPの概要やLMSとの違い、導入のメリット・デメリットを解説します。
<この記事の要約>
LXPとは「学習者一人ひとりの体験を最適化する学習プラットフォーム」
個々の関心やスキルに応じてコンテンツを自動提示し、従来の画一的な教育と異なるパーソナライズ学習を実現。モバイル対応や社内外の知識統合が強みになる。
LXP導入の背景は「DX化と教育ニーズの多様化」になる
DX推進やモバイル学習の普及、コンテンツ多様化により、従業員の主体性や習熟度に応じた柔軟な学習環境が求められるようになった。
導入メリットは「学習モチベーション向上・定着・交流促進」になる
個別最適化された学習によりモチベーションと定着率が向上。関連する受講者同士の交流機能もあり、学びの継続と企業文化としての知識共有を促進する。
LXPとは
LXPは正式名称を「Learning Experience Platform(ラーニング・エクスペリエンス・プラットフォーム)」といい、日本語に訳すと「学習体験プラットフォーム」という意味です。LXPの特徴は、学習者の好みや要望にマッチしたコンテンツを、自動的に提供できる点にあります。
イメージしやすい例としては、インターネットの通販サイトが挙げられるでしょう。サイトで商品を検索すると、そのユーザーが関心を示しそうな関連商品が自動的に表示されます。
このようにLXPは、ユーザーの関心が高いと思われる内容を、社内外の優良な教育コンテンツから抽出し提示してくれます。自社で用意したコンテンツだけでなく、インターネット検索サイトやSNS上のコンテンツも連携が可能であり、LMSよりも自由度の高い運用ができる点が大きな特徴です。
LXPとLMSの違い
LXPとよく似ており、混同しやすい仕組みにLMSがあります。
LMSとは「Learning Management System(ラーニング・マネジメント・システム)」のことで、日本語にすると「学習管理システム」という意味になります。LMSは「学習管理」とあるように、決まったカリキュラムを対象の受講者に提供し、受講状況を管理するシステムです。
LXPとLMSとの違いを、以下で一覧表にまとめました。
【LXPとLMSの比較】
| LXP(学習体験プラットフォーム) | LMS(学習管理システム) | |
|---|---|---|
| 特徴 | 個々の学習者が学習内容を選択でき、自発的な学習を促せる | 管理者が必要と判断する学習内容を配信し、受講状況を管理できる |
| 学習コンテンツ | 自社で選定したコンテンツの他、インターネット上に公開された記事や音声コンテンツも提供できる | 自社で選定したコンテンツのみを提供する |
| 機能 |
|
|
| 強み | パーソナライズした学習を提供できることにより、モチベーションを維持したままスキルアップが可能になる | すべての対象者が知っておくべき知識(コンプライアンス等)の定着化に効果がある |
| 弱み | 長時間のコンテンツ配信には不向き 多機能なため、使い方のレクチャーが必要 |
画一的な学習コンテンツしか提供できない 個々の学習ニーズに対応しにくい |
LMSの詳細については、「LMSとは|学習管理システムのメリットと導入のステップ・選定ポイントを解説」で解説していますので、ご覧ください。
LXPの開発が可能になった背景
LXPは、個々の学習者のニーズに応じたコンテンツを、提供できる点が大きな強みです。学習者のニーズは業務経験を通じて生まれるものであり、そのニーズを満たす学習コンテンツを提供できる点において、LXPは経験重視の学習プラットフォームといえます。
LXPのような仕組みが構築されたのは、以下に挙げる3つの背景によります。
- DXの急速な進展
- モバイルデバイスの普及
- コンテンツの増加と多様化
DXの急速な進展
DXとはデジタル・トランスフォーメンションの略で「IT・デジタル技術を用いて、ビジネスモデルを変革し、競争優位を生み出すこと」と捉えられています。
経済産業省がまとめたデジタルガバナンスコードによると、DXは以下のように定義されています。
”企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。”
出典:『デジタル・ガバナンスコード3.0』経済産業省 2024年9月19日
多くの企業はDXに取り組むことにより、業務効率化にとどまらず、新たなビジネスモデルを構築するなど成果を上げてきました。
人材育成関連の分野も例外ではありません。DXの進展は企業の人材育成においても進化をもたらし、LXPのようなこれまでにない学習の仕組みの構築を可能にしたのです。
デジタルガバナンスコードについて、理解を深めたい方は、「経済産業省のデジタルガバナンスコード(旧・DX推進ガイドライン)とは」参考にしてください。
身近なルーチン業務からはじめられるDXとは?
自社のDXを推進しようと検討するものの、何から始めたらいいかわからない、また、社内の複数部署で合意形成を取る難易度が高い…と考えている方へ。
まずは、「身近な業務のDX化」から検討するのが得策です。ぜひ、無料のお役立ち資料からご確認ください。
\こんな方におすすめの資料です/
- DXと言っても何をすればいいかわからない
- まずは身近なところからクイックにできるDXを試したい
- 目の前のルーチン業務を効率化したい
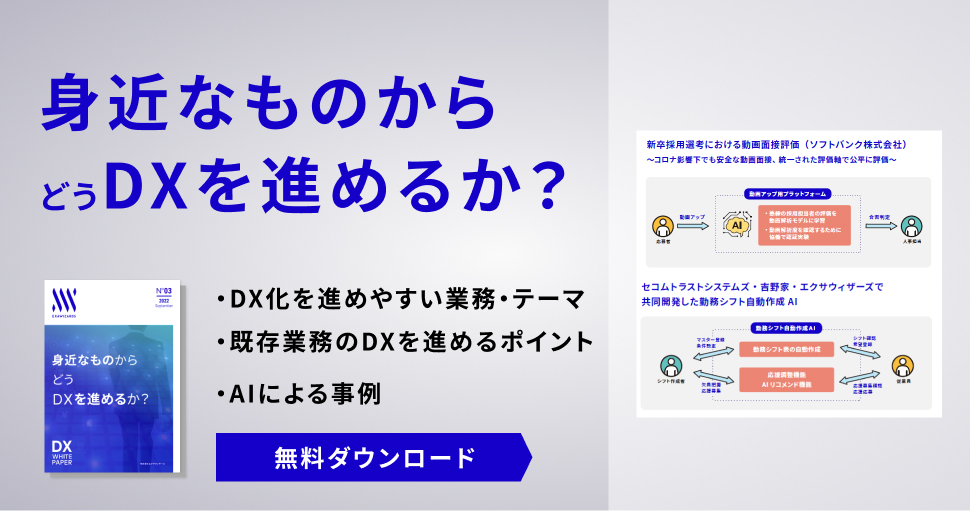
モバイルデバイスの普及
スマートフォンやタブレットなどのモバイルデバイスは急速に普及し、インターネットに接続できる環境であれば時と場所を選ばず、誰もが必要なコンテンツにアクセスできるようになりました。
こうした変化は、新しい学習スタイルの構築にも影響を及ぼし、モバイルデバイスを利用したプラットフォームの開発が進みます。LXPはスマートフォンやタブレットからもアクセスできるため、時と場所に縛られない学習が可能になりました。
コンテンツの増加と多様化
インターネット上には膨大な情報が公開されており、ユーザーは多様なコンテンツから情報を得ています。また、SNSの普及により、情報を他者と簡単に共有できるようになりました。
このようにコンテンツが増加し多様化するなか、有益な情報を学習に活用したいというニーズが高まります。情報が豊富で多様性に富んでいるほど、LXPを用いた学習は効果を上げることができるのです。
人材育成にLXPを活用するメリット
画一的な研修をおこなうよりも個々の人材に応じたカリキュラムを提供したほうが、学習効果が高まります。以下で、人材育成にLXPを活用するメリットを挙げます。
- 個々の従業員に適したカリキュラムを提供できる
- 学習者のモチベーションが向上する
- 企業課題に応じた教育カリキュラムをカスタマイズできる
- モバイルデバイスを活用した学習を提供できる
- 学習者間の交流を促進できる
- 学習スピードが向上する
- 学習内容が定着しやすい
個々の従業員に適したカリキュラムを提供できる
従来のような画一的な研修の提供にとどまらず、学習者個々のニーズに応じたカリキュラムの提供が可能になる点がメリットです。
同じ業務を担当していても、個々の人材の習熟度の違いにより、必要とする知識やスキルのレベルは異なってきます。LXPを学習に用いることで、こうしたレベルの違いに応じた効果的なコンテンツの提供が可能になるのです。
学習者のモチベーションが向上する
従来の画一的な研修コンテンツでは、習熟度の高い人にとっては簡単すぎる内容であったり、反対に習熟度が低い人にとってはレベルが高すぎて、モチベーションが維持できないという問題がありました。
LXPでは、個々の学習者が今必要とする情報がタイムリーに提供されるため、高いモチベーションを維持したまま学習に臨めます。多くのコンテンツから自分が必要な情報を取捨選択できる点も自発的な学習を促すことにつながり、学びに対する意識の向上をもたらすでしょう。
企業課題に応じた教育カリキュラムをカスタマイズできる
LXPでは、提供する学習コンテンツを自由にカスタマイズできます。課題解決に必要なコンテンツを、意図的に多く配分するといったことも可能です。たとえば、風通しの悪さが情報共有を阻害しているといった課題があれば、コミュニケーションに関するコンテンツを充実させます。
また、課題や弱点の克服ではなく特定の強みがあれば、その強みをさらに増幅させるようなコンテンツを充実させることも可能です。
モバイルデバイスを活用した学習を提供できる
スマートフォンやモバイルデバイスを用いた、時間と場所を選ばない学習を提供できる点もメリットです。多くの働き手にとって、学習のためにまとまった時間を取ることは困難です。さらに昨今、働き方改革が進められるなか、就業中に学習のための時間を確保することは難しくなってきました。
LXPによりモバイルデバイスで学習ができる環境が整えば、通勤中などの隙間時間を有効に活用できます。まとまった時間を取れずとも、高い学習効果が期待できるでしょう。
学習者間の交流を促進できる
LXPには、学習者どうしの交流を促進する機能を搭載したものもあります。LXP上でユーザーどうしが意見や情報を交換できるため、相互の刺激になりモチベーションも向上するでしょう。
LXPによっては、同じコンテンツを受講した他のユーザーをフォローできるものもあります。こうしたつながりによって、切磋琢磨できる環境が構築され、学習効果が高まる点も大きなメリットです。
学習スピードが向上する
以前は自身が興味・関心を持った分野を学習しようとすれば、適したコンテンツを自分で探す必要があり多くの時間を要していました。しかし、LXPがあれば過去の受講履歴や検索履歴から、適したコンテンツが自動で提供されます。
必要とする学習内容が目の前に表示されるため、コンテンツを探す時間が大幅に短縮でき、学習スピードが向上するのです。
学習内容が定着しやすい
LXPによる学習では「マイクロラーニング」の手法を取り入れた教材が多く使われます。マイクロラーニングとは、1分から5分程度の短時間で完結する教材を反復学習する手法です。
マイクロラーニングのコンテンツは、動画の視聴やクイズ形式による教材が多く、短時間の集中した学習に適しています。隙間時間を活用して反復学習をおこなうことにより、学習内容の定着化が図りやすい点がメリットです。
LXPを導入する際の注意点・デメリット
一方で、LXPには以下に挙げるようなデメリットも存在します。導入を検討する際には十分な注意が必要です。
- 長時間のeラーニングには向いていない
- 教育コストが増加してしまう
- 管理者の負担が増加する
- 制度面の整備が必要になる
長時間のeラーニングには向いていない
LXPは、マイクロラーニングの手法を用いた短時間のコンテンツで、隙間時間を有効活用する学習スタイルに向いています。そのため、じっくりと机についてコンテンツを視聴する学習スタイルには向いていません。
もし、これまで自社で蓄積してきた教材が、長時間のeラーニングばかりであれば、コンテンツの再構築が必要になってくるでしょう。コンテンツ再構築が必要な場合、かかるコストや時間を考慮の上、導入を進めなくてはなりません。
教育コストが増加してしまう
LXPを導入するにあたって、費用がかかる点は考慮しておくべきです。導入に関する初期費用だけでなく、1ユーザーアカウントあたりで使用料がかかるなど、ランニングコストも発生します。
教育コストが増加することは避けられないため、従業員数の多い企業の場合、導入初期は対象者を限定しスモールスタートではじめ、様子をみながら対象を広げていくといったことも考えなければなりません。
管理者の負担が増加する
LXPは多機能であるものが多く、導入にあたっては入念なレクチャーが必要になってきます。とくに導入初期においては、利用者に対する説明会の開催や質問への対応など、管理者の業務量は増えてしまうでしょう。
運用が軌道にのっても、コンテンツの改廃をこまめにおこなう必要があるため、管理者の負担増は避けられません。
制度面の整備が必要になる
LXPを導入して学習を促していくためには、制度面の整備も進めなくてはなりません。そもそも隙間時間を学習にあてることを推奨するのであれば、業務時間にカウントすべきか否かルール決めをする必要があります。
セキュリティー面においても、個人端末の利用制限などのルールを明確にしておかなければ、学習コンテンツの外部流出などが生じる恐れがあります。
LXPを活用して効果的な学習を推進するためのポイント
LXPを人材育成に活用することにより、効果的な学習の推進が可能になります。効果を最大限発揮するためには、以下のポイントに留意して導入を進めましょう。
- 常に最新の情報をアップデートする
- 常に学習者の状態を把握する
- 実務と直結したコンテンツを用意する
常に最新の情報をアップデートする
学習コンテンツの鮮度については、十分な留意が必要です。タイムリーな学習コンテンツを提供するというLXPの特性上、古い情報が提供されることは学習効果を大きく低下させます。
業界情報や仕事に関するスキルは、常にアップデートされています。古い情報を提供してしまうと学びなおしが必要になり非効率であるため、常に最新のものに差し替えなくてはなりません。
新しい情報を入手する重要性については、「アンラーニングとは?企業に変革を促す実践的な方法と注意点を解説」でも解説していますので、ご確認ください。
常に学習者の状態を把握する
学習者ごとの利用頻度を確認し、状態を把握しておきましょう。学習頻度の低い個人・部署には利用を促すなどして組織全体で意識のばらつきを防ぐことで、総合的に学習効果が高まります。
また、よく学習されているコンテンツに注目することで、経営層が気が付かなかった課題を発見できるケースもあります。
実務と直結したコンテンツを用意する
学習者の意欲を向上させるには、実務と直接的に関連するコンテンツを用意することが効果的です。研修等で学んだ知識は、実務で実践することで定着していくものです。
また、今担当している業務で不明点があれば、LXPで学習しすぐに解決できることで業務スピードが向上します。こうしたことを繰り返していけば、わからないことがあればすぐに自発的に学習する習慣が身についていきます。
LXPを導入した企業事例
ここではLXPを導入し、人材育成の再構築を図った企業の事例を紹介します。
以下、2つの企業事例をみてみましょう。
- 日立グループ
- 旭化成株式会社
LXP以外にも、DXの導入により成功を収めた企業は多数あります。「【2024年最新版】DX事例集|国内外・自治体や中小企業まで自社に合ったDXの成功事例を見つけよう」を参考にし、導入を検討していきましょう。
日立グループ
日立グループでは、国内企業では先駆けてLXPの導入に踏み切りました。同社は「イノベーションを生む組織と人材の実現」を基本理念に掲げ、その取り組みの一つとして「ジョブ型人材マネジメント」への変革を目指します。
そのためには、会社が必要なポストや仕事を明示し、従業員自らがそれに手を挙げることで、自身のキャリアを強く意識する組織への変革が必要になります。社員一人ひとりが、自身のキャリアを深く考え実現するためには、継続的な学びが欠かせません。そこで、いち早くLXPに着目し、社員教育体制の再構築を図りました。
本格的なLXP導入を前に、グループ社員300名に意識調査をおこなったところ、導入に対し好意的な意見が大半を占めます。その意見の多くは、研修参加などまとまった学習時間を取る必要がなく、学びに対するハードルが下がることで、意欲的に取り組めるといったものでした。
LXPの実装においては、これまで日立グループで活用してきた学習ツールと、Web上に存在するさまざまな学習コンテンツとの連携を可能にしました。数分で完了するものから、数時間かけて視聴するものまで、多様なコンテンツを用意しています。
はじめに強化したいスキルを登録しておけば、それに応じたコンテンツが表示されるため、従業員は気軽な気持ちで学習に取り組めるようになったようです。個々の学習内容はオープンにされているため、同じコンテンツを学習した従業員どうしでコミュニケーションが生まれるなど、副次的な効果も現れているとのことです。
参照:『自分のキャリアを自分でつくる。 学びをもっと身近に、LXPによる新しい学習体験。』株式会社日立アカデミー 2024年12月参照
旭化成株式会社
旭化成株式会社では「人は財産、すべては『人』から」をスローガンとして、さまざまな人材育成・支援制度の構築に取り組んでいます。その取り組みの一つとして、社内外のコンテンツから学習者のニーズに沿った講座を受講できる「CLAP (Co-Learning Adventure Place)」という、プラットフォームを開発しました。
CLAPは、これまでの社内知見から構築した独自の学習コンテンツに加え、外部サービスのeラーニングコンテンツと連携。キャリアの可能性を広げる『学びの幅(好奇心)』と専門性を深める『学びの深さ(専門性)』ためのコンテンツを無償で提供しています。
CLAPの導入以前は、階層別の集合研修が人材育成の中心であり、LMSにより受講実績を管理していました。しかし、キャリア意識の多様化が進むなか、各部門・各業務で求められる専門的なスキル習得のニーズが発生します。こうしたニーズに対応する形で、LXPの導入に踏み切りました。
同社はまず、国内のグループ会社勤務の従業員約2万人を対象に、CLAPの利用をスタートします。利用開始から3カ月半で、対象者の81%が登録、1つ以上のコンテンツを受講した人が6割を超えるなど、導入初期から高い利用率を達成しています。(2023年3月31日時点)
あるグループ会社では、個々が興味を持って学んだコンテンツを紹介しあう活動が自発的に始まるなど、組織全体に学びに対する意欲の向上がみられたとのことです。
参照:『採用ホームページ 人財育成・支援制度』旭化成株式会社 2024年12月参照
参照:『旭化成株式会社:次の100年に向けて新たな人財戦略を推進』コーナーストーン 2024年12月参照
DX推進を成功させる、社内を動かす・うまく巻き込むコツとは?

画像バナー入る
DXを成功させるためには、社内を動かし、うまく巻き込むことが重要です。その中でも特に経営層を中心にアップダウン的に実施することで、DX人材の育成をより加速させることができます。
本資料では、DX推進・人材育成に不可欠な「経営層の巻き込み」について詳しく解説しています。ぜひダウンロードしてお役立てください。
\こんな方におすすめの資料です/
・DX人材育成の必要性は理解しているが、実際の推進が難しい
・経営層の理解と協力が得られず、人材育成が進まない
・全社的なDX推進のために経営層の協力が必要
・DX人材育成の取り組みを社内で加速させたい
・経営層を巻き込んだDX推進の成功事例を知りたい
まとめ
企業事例からもわかる通り、会社の発展には所属する従業員が自発的に学ぶことで、成長を喜びと感じられる環境が欠かせないようです。これまでの画一的なコンテンツで与えられる学びでは、こうした環境の構築には限界があるでしょう。
個々の従業員のニーズに沿った学びをタイムリーに提供できる点で、LXPは画期的なプラットフォームであるといえます。従業員にとっても、業務に求められるスキルが多様化するなか、今必要なコンテンツがタイムリーに手に入ることは、大きなメリットではないでしょうか。
人材育成に課題を持つ企業は、ぜひLXPの導入を検討してみてください。
DX人材育成サービス「exaBase DXアセスメント&ラーニング」とは
- 自社のDXが思うように進まない
- DXに対する従業員の意識が上がらない
このような課題を抱える企業は多いのではないでしょうか。理想的な形でDXを進めていくには、DXの推進役となるDX人材の育成が欠かせません。
エクサウィザーズが提供する、DX人材育成サービス「exaBase DXアセスメント&ラーニング」は、実務で活躍するDX人材の効果的な育成をサポートします。
「exaBase DXアセスメント&ラーニング」3つの特徴
「exaBase DXアセスメント&ラーニング」は、自社の現状把握から会社全体のDXリテラシーの底上げ、専門人材の育成まで、DX人材育成をトータルで伴走支援するサービスです。
特徴1.デジタルスキル標準に完全準拠したデジタルイノベーターアセスメント「DIA3.0」
効果的なDX人材育成には適切なアセスメントを実施し、従業員の現状を可視化し育成計画を策定することが有効です。
デジタルイノベーターアセスメント「DIA3.0」は、デジタルスキル標準に準拠した形で、組織全体のDXリテラシー・DX推進スキルの両方を測定可能です。
全社員のDXリテラシーやマインド・スタンス」から「DXを推進する人材の各種スキル」までを網羅的に可視化することで、DX人材の選抜や育成計画の策定が可能になるでしょう。
特徴2.人材要件の定義と育成計画策定もご支援
DX人材の育成にはゴールとなる人材要件の定義が欠かせません。「DIA3.0」によるアセスメントの結果をもとに、自社個別の状況や要望を考慮した人材要件の策定が可能です。
現状とゴールが策定されれば、そのギャップを埋める育成計画が必要です。育成する人数・育成レベル・必須スキルなどを定義し、どのようなコンテンツでいつまでに育成するのか、育成計画の策定を支援します。
特徴3.個人に最適化された育成プログラムの提供
策定された育成計画に基づき、パーソナライズされた育成プログラムの提供も可能です。
全社的なDXリテラシーの底上げが急務であれば、アセスメントとeラーニングを効果的に提供する「DXリテラシーコース」を全社員で受講することが有効です。
また、「DXパーソナライズプログラム with Udemy Business」では「DIA3.0」の結果をもとに個人に最適化されたUdemy Busines内の講座が自動的にレコメンドされます。個々の受講者にとって、今必要な知識やスキルをタイムリーに習得できます。こうしたLXPの環境を整備することにより、専門人材の早期育成が可能になるでしょう。
そして、自社の個別のニーズに対しては、集合研修の開催も可能です。より実践的なアウトプット中心のカリキュラムによりスキルの定着化を支援します。
効率的にDX人材を育成するには、個々の受講者の学習進捗の管理と、それぞれに適した学習内容のレコメンドが欠かせません。「exaBase DXアセスメント&ラーニング」は、LMS・LXPとしての機能を有しており、高い学習効果が期待できます。
これにより、全社的なDXリテラシー向上と専門人材の早期育成が可能となるでしょう。

