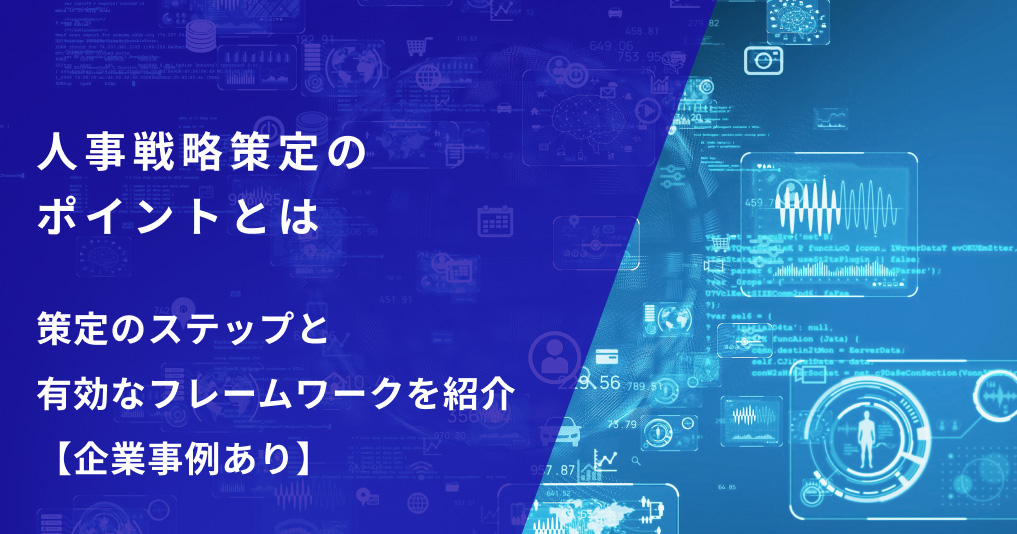企業の持続的な発展には、人材活用の最適化が欠かせません。しかし、昨今の社会情勢の変化や人材不足、多様性への対応など、人材を取り巻く状況は流動性を増しています。
こうしたなか、企業には明確な人事戦略に基づいたかじ取りが求められます。
この記事では、人事戦略の重要性から策定のステップ、有効なフレームワークを解説。優れた人事戦略で成果を上げている企業の事例も紹介します。
人事戦略とは
人事戦略とは、重要な経営資源である人材に関わる業務を改善し、組織の活性化や生産性の最大化を目指す取り組みです。採用・育成・配置・処遇・定着といった、人材に関わるあらゆる業務にアプローチします。
- 人材確保が思うように進まず事業成長に影響が出ている
- 人材育成が進まず社員の成長が鈍化している
- 適材適所の人員配置が進まずマンパワーを活かしきれていない
こうした課題は多くの企業が抱えており、解決を図らなければ将来的な組織成長が見込めないばかりか、現在の事業活動にも影響を及ぼしかねません。自社にマッチした人事戦略を策定し実行することによって、さまざまな人事課題の解決を図る必要があるのです。
人事戦略と戦略人事の違い
人事戦略と混同しがちな用語に、「戦略人事」というものがあります。戦略人事とは「戦略的人的資源管理(Strategic Human Resources Management)」の略で、人的側面から経営戦略実現に向けアプローチする手法を指します。
| 内容 | 例 | |
|---|---|---|
| 人事戦略 | 人材に関わる業務改善のための戦略 |
|
| 戦略人事 | 経営戦略実現に向けた戦略的な人事活動 |
|
人事戦略は組織成長を意図した人的施策を指すのに対し、戦略人事は経営と密接に関わり、経営課題解決に向け、より特化した人的施策の取り組みといえるでしょう。
人事戦略が重視される背景
DXの進展やグローバル化の推進をはじめ、社会情勢の変化スピードが高まるなか企業が持続的に発展するには、より強固な組織体制を構築する必要があります。その根幹となるのが人材であり、適切にアプローチすることで力を最大化しなくてはなりません。
しかし、少子高齢化にともない人材確保が困難を極め、事業継続に必要な人員確保も難しい状況が続いています。さらに人材の多様化も進み、従来のような画一的な人事管理が通用しなくなりました。こうした情勢の変化に対応しながら限られた人的資源を有効に活用し、事業成長につなげていくために優れた人事戦略が必要となるのです。
人事戦略の目的
人事戦略の大きな目的は、組織強化を図り生産性を最大化することにあります。例えば、組織成長を見越した人材基盤の整備のために採用活動を強化したり、従業員のモチベーションとパフォーマンスを向上させるために、評価制度や教育を見直したりといった取り組みです。自社のビジネスを成長させるには、こうした人事課題はタイムリーに解決する必要があります。その解決を図ることが人事戦略の目的です。
もし人事戦略がなかったり、適切でなければさまざまな問題が生じます。ミスマッチによる早期離職が頻発し事業運営が困難になったり、既存の従業員もキャリアの見通しが立たずモチベーションを低下させ幹部の後継者が育たなかったりと、事業成長の鈍化を招いてしまうのです。
人事戦略の構成要素
ここでは人事戦略を構成する4つの要素について、確認していきましょう。
- 採用
- 育成
- 配置
- 定着
いずれの要素も重要であり、事業活動の維持・拡大に欠かせないものです。それぞれの戦略のポイントも踏まえ解説します。
採用
採用は企業活動における、最重要課題といっても過言ではありません。人材が入ってこない限り、新たな事業へのチャレンジや既存事業の拡大が見込めなくなるためです。将来にわたり事業を継続するためには、バランスの良い世代構成で人員を確保していく必要があります。また幹部の育成も課題であり、その担い手となる若手人材も一定数確保しなくてはなりません。
新規事業の立ち上げや既存事業の拡大など状況によっては、すぐに戦力となるスキルを持った人材を中途採用しなくてはならないケースもあります。それぞれの局面に応じて必要とする人材を確保するために、戦略性に基づいた採用活動が求められるのです。
育成
採用した人材に力を発揮してもらうためには、組織としての計画的な育成が欠かせません。採用と同様に育成は、企業にとって重要です。育成戦略では、新人からマネジメント層まで、各階層に応じた施策が必要になります。新入社員にはビジネスマナーをはじめとした企業人としての基礎を学んでもらい、マネジメント層には経営に関する広範な知識を定着させなければなりません。
また、それぞれの職種における必要な知識やスキルを習得するための、専門的な教育も必要です。それぞれの階層の業務に必要なスキルだけでなく、力を発揮してもらうためのマインドも含め、体系的な育成施策を構築する必要があるのです。
配置
戦略的な人員配置も組織力向上に欠かせない要素です。多くの人材は、自身のスキルや特性が活かせる環境において、高いモチベーションで業務に臨みます。組織として人材の力を最大限に活かしていくためには、こうした適材適所の人員配置と業務分担を実現する取り組みが必要です。
そのためには、それぞれの人材の保有スキルや特性、本人の希望を把握する必要があります。そのための具体的な施策としては、タレントマネジメントシステムの導入が挙げられるでしょう。どのようなスキルを持った人材がどれくらいいるのか、全社的に把握することが、多くの人材がモチベーション高く働ける環境構築の第一歩となるのです。
定着
人材が退職することは、企業にとって大きな損失です。特にキーパーソンとなるような人材が欠けた場合、事業計画が頓挫することもあるほどです。コスト面での損失も計り知れません。これまで費やしてきた採用・育成に関わるコストが無駄になるだけでなく、新たに追加のコストが発生してしまいます。
こうした事態を避けるためにも、人材の定着に対する施策も戦略的におこなう必要があります。定着に向けた施策は、さまざまなアプローチが考えられます。まず、ワークライフバランスが実現できる労働環境の整備は最低限おこなうべきでしょう。納得度の高い評価制度の再構築や、他社にはない魅力的な福利厚生の提供など、エンゲージメント向上の取り組みもおこなう必要があります。
人事戦略策定に有効なフレームワーク
人事戦略の策定には組織と人材の現状を把握し、本来あるべき姿とのギャップを正しく把握する必要があります。その際に有効なものが、各種フレームワークです。
人事戦略策定の各フェーズでフレームワークを用いることにより、思い込みや主観を排除した現状把握が可能になります。また、フレームワークを用いた分析を関係者が共同で作業することにより、共通認識の醸成が図れる点もメリットです。
以下、人事戦略策定時に有効なフレームワークを紹介します。
SWOT 分析
SWOT分析は、現状分析をおこなう際に有効なフレームワークです。主にマーケティング領域で用いられることが多い手法ですが、人事戦略の策定においても活用できます。
分析の対象を以下の四象限に分類し、組織や人材の現状を浮き彫りにしていきます。
- 自社の内部環境の「強み(Strengths)」
- 自社の内部環境の「弱み(Weaknesses)」
- 自社を取り巻く外部環境の「機会(Opportunities)」
- 自社を取り巻く外部環境の「脅威(Threat)」
それぞれの要素を洗い出し、付箋に記入するなどしてそれぞれの象限に分類していきます。この作業によって、自社の伸ばすべき「強み」や克服すべき弱点、追い風となる外部環境、警戒すべき外部要因が明確になります。自社の置かれた状況を客観的に把握できるでしょう。
【製造業の採用活動における SWOT分析の例】
強み(Strengths)
|
弱み(Weaknesses)
|
機会(Opportunities)
|
脅威(Threat)
|
TOWS分析
TOWS分析はSWOT分析の発展形で、クロスSWOT分析とも呼ばれます。SWOT分析で可視化された要素をそれぞれの項目ごとにかけ合わせ、より具体的な分析をしていく手法です。
- 「機会(Opportunities)」✕「強み(Strengths)」
- 「機会(Opportunities)」✕「弱み(Weaknesses)」
- 「脅威(Threat)」✕「強み(Strengths)」
- 「脅威(Threat)」✕「弱み(Weaknesses)」
こうした分析により、それぞれの要素に対する的確な判断が下せるようになります。例えば、「機会(Opportunities)」✕「強み(Strengths)」にピックアップされた要素では、積極的にコストをかけるなどして取り組めば大きな効果が得られます。反対に、「脅威(Threat)」✕「弱み(Weaknesses)」に洗い出された要素は、より慎重にディフェンシブな施策を講じるという判断になります。
【製造業の採用活動における TOWS分析の例】
【SO戦略】強み × 機会
|
【WO戦略】弱み × 機会
|
【ST戦略】強み × 脅威
|
【WT戦略】弱み × 脅威
|
ロジックツリー
ロジックツリーは一つの課題に対し、おこなうべきアクションを洗い出していくのに適したフレームワークです。まず解決すべき課題を挙げ、その解決に向けた大まかな方針を枝分かれさせ右側に記入します。さらに枝分かれさせた方針ごとに、取るべきアクションを細分化しツリー上に記入していきます。
課題から解決に向けた大まかな方針、それぞれの具体的なアクションがツリー上に構成されるため、解決に向け取るべき行動の優先順位とその道筋が明確になります。
【ロジックツリーの例】
| 年間新卒採用数を20人から40人に倍増させる |
|
|
|
|
VRIO分析
VRIO分析とは社内リソースの評価に用いられる手法です。もちろん人的リソースの評価にも活用されます。VRIO分析ではリソースを以下、4つの視点で分析していきます。
| Value(経済的価値) | 競合優位の状態をもたらす価値の高いリソース |
|---|---|
| Rarity(希少性) | 競合が持ち得ない自社独自のリソース |
| Imitability(模倣可能性) | 自社のリソースが模倣される可能性についての評価 |
| Organization(組織) | リソースを活用し続ける組織能力に対する評価 |
こうした視点で自社の採用力や育成力を分析すれば、競合優位性や自社の独自性を把握できます。それをもとにより確度の高い人事戦略の策定が可能になるでしょう。
【VRIO分析の例 自社の育成力に関するリソースの評価】
| 視点 | 分析 | 評価 |
|---|---|---|
| Value(経済的価値) | 長期雇用を前提とした計画的な人材育成により技能伝承が進み、生産性・品質が維持されている。 | ◎ 高い経済的価値あり |
| Rarity(希少性) | 多能工育成やメンター制度、OJT+OFF-JTを組み合わせた独自プログラムを有している。 | 〇 一定の希少性あり |
| Imitability(模倣可能性) | 経験豊富なベテラン社員による指導や、現場文化に根ざした育成ノウハウは模倣が難しい。 | ◎ 模倣は困難 |
| Organization(組織) | 育成方針が部門横断的に制度化されているが、教育担当者が不足している。 | 〇 活用体制は整っているが、人的リソースが不足 |
人事戦略の立て方6ステップ
ここでは、人事戦略の立て方を6ステップで解説します。以下のステップに沿うことにより、経営戦略との整合性が担保された人事戦略を策定できます。
- 経営戦略の確認
- 経営戦略に基づいた人事目標の設定
- 現状把握と情報収集
- 具体的な施策と計画の策定
- 施策の実行
- 効果・検証
1.経営戦略と現場の状況の確認
人事戦略は、経営戦略に基づいたものでなくてはなりません。経営戦略との整合性がない人事戦略は組織内に混乱を招き、さまざまな弊害をもたらすでしょう。
また、各部署・部門の状況を把握することも大切です。人事戦略は、各部署の人員数に関わる施策となるケースもあるためです。人事戦略により、極端に人員削減が発生する部門があるようなときは、業務量とのバランスを考慮するといった配慮が必要です。
2.経営戦略に基づいた人事目標の設定
経営戦略と現場の状況を確認したのち、経営戦略実現に向けた人事目標を設定します。例えば、「5年後に営業拠点を全国に3カ所増やす」といった経営戦略であれば、「各拠点に配属する10名の営業人材の採用を目標にする」というイメージです。
人事目標の設定は、曖昧さを排除することが大切です。人数のように数値化できるものは数値化することで達成度合いが明確になり、確実な達成に向けた行動が取りやすくなります。
【人事目標の具体例】
| 定量的な目標 | 定性的な目標 |
|---|---|
|
|
3.現状把握と情報収集
人事目標が設定できたら、現状把握をおこない目標と現状のギャップを確認します。このプロセスで各種フレームワークを用いれば、自社の現状を客観的に把握できるでしょう。
現状把握は自社の状態だけでなく、外部環境にも目を向けることが必要です。同業他社の動向をはじめ経済の見通しや国際情勢まで、幅広く情報収集をおこないます。自社の追い風となる要素や、脅威となりうる事象について正確に把握しましょう。
4.具体的な施策と計画の策定
目標と現状のギャップが明確になったら、ギャップを埋めるための具体的な施策を検討します。ロジックツリー等のフレームワークを用い、課題解決に向け実行すべき取り組みを決めていきます。
取り組みが決まれば、次に綿密な計画を立てましょう。各取り組みの期限を決め、いつまでに完了するのか、関係者で共有し共通認識とします。
5.施策の実行
計画をもとに各施策を実行するプロセスです。施策を実行するなかでリソースが不足するようであれば、適宜外部サービスを活用するなど柔軟に対応していきましょう。
施策を実行するなかで、現場への理解を促す活動も合わせておこないます。丁寧に説明をして理解を深めてもらうことで、人事戦略の浸透を図りましょう。現場の理解が進めば協力が得られるようになります。計画が進みやすくなるばかりでなく、施策の効果も高まるでしょう。
6.効果・検証
人事戦略に基づいた施策がひと段落したら、定期的に検証する体制を整えましょう。人事戦略を実行したことにより、どのような効果が得られたのかモニタリングすることで、次の戦略につなげていかなくてはなりません。
採用人数など定量的な目標であれば、成果を可視化することは比較的容易です。しかし、従業員満足度など定性的な目標については、適宜サーベイを実施するなど外部サービスを活用することも検討しましょう。
質の高い人事戦略を実行するポイント
質の高い人事戦略を実行するためには、以下のポイントを押さえることが大切です。現場の理解を得ながら、確実に実行していきましょう。
- 経営戦略との整合性を常に確認する
- 変化に応じ柔軟に対応する
- 必要に応じて外部サービスを活用する
経営戦略との整合性を常に確認する
人事戦略を実行する際は、経営戦略をはじめとした社内のあらゆる方針と整合性を担保する必要があります。そのためには、経営層や各部門責任者と常に連携し、確認できる体制を構築することが必要です。
人事戦略は、経営戦略実現のための一つの手段である認識を常に持ちつつ、世の中の動向を踏まえ実行されなくてはいけません。
変化に応じ柔軟に対応する
人事戦略を実行する過程で、状況が変化することもあるはずです。また、当初の計画通りに進まないこともあるでしょう。その際は状況に応じて柔軟に対応することも必要です。
特に実行している施策が現場の理解を得られず、従業員の疑念やモチベーションの低下につながっているようであれば早急に対応しなくてはなりません。経営戦略から逸脱をしない範囲で、柔軟な対応をしていきましょう。
必要に応じて外部サービスを活用する
人事戦略を実行するうえで、リソース不足が障害となることもあるでしょう。そのときは必要に応じて、外部リソースを活用することをおすすめします。例えば、タレントマネジメントや各種サーベイなどの活用です。こうしたツールは、クラウド型のサービスが各社から提供されており、活用することでリソース不足のかなりの部分は補えるはずです。
費用の負担は発生しますが、すべてを内製化しようとして時間がかかることを考えれば、必要な投資として十分な費用対効果が得られるでしょう。
企業の人事戦略の好事例を紹介
ここでは優れた人事戦略により成果を上げた企業の好事例を紹介します。
- オムロン株式会社(コア人材の適材適所配置)
- 楽天株式会社(Back To Basics Projectの取り組み)
- パナソニックホールディングス株式会社(人材育成と多様な人材の活用)
3社の事例を見ていきましょう。
オムロン株式会社(コア人材の適材適所配置)
オムロン株式会社では「グローバルコアポジション・コア人財戦略」と題して、コア人材の適材適所配置を実現する取り組みを実行しています。オムロングループの事業と経営を牽引する重要なポジションを「グローバルコアポジション」と位置づけ、200を超えるポジションに役割に適した人財を配置しています。
コア人財の選定は、関連部門と経営層の協議のうえ、最終的には社長が人選します。選ばれたコア人材には、自身の後継者を選び責任を持って育成することが義務付けられます。また次の後継者候補として、35歳未満の社員を対象に次世代リーダーとして人選し、計画的な育成の取り組みも実践しています。
楽天株式会社(Back To Basics Projectの取り組み)
楽天株式会社は、「グローバル イノベーション カンパニー」として、世界に通用するサービスを生み出すことを目指しています。その実現のために、人材への取り組みを強化すべく、2017年より「Back To Basics Project」を立ち上げ、採用・育成・定着を3つの柱とした人事戦略を展開しています。
各分野の取り組みと成果は以下の通りです。
| 採用 | 採用プロセスの改善と採用ブランディングの強化への取り組みが功を奏し、採用人数の確保だけでなく、外部機関からの一定の評価を得るに至った。 |
|---|---|
| 育成 | 1on1ミーティングを制度化し全社導入したことにより、社内コミュニケーションが活性化。管理職向けのフィードバック研修を実施し、受講者から90%の高い満足度評価を得ている。 |
| 定着 | パフォーマンスが正当に評価されるよう、評価・報酬制度を刷新。従業員のニースに合わせた多様な働き方の提供。「人材育成マップ」による中長期的なキャリアプランの明確化が進む。 |
こうした取り組みをスピーディーにおこなうことにより、「勝てる人材、勝てるチームを作る」という楽天の人事における基本目標を実現し、組織基盤の強化を図っています。
参考:Corporate Topics:「Back to Basics Project」(楽天株式会社)
まとめ
多様性が進み人材を取り巻く状況が流動性を増すなか、人事部門は優れた人事戦略に基づいた人事施策を実行し、経営戦略の実現に寄与しなくてはなりません。これまでの定型的な処理業務を中心におこなう人事部門ではなく、より戦略性の高い施策を経営層に提案することが求められるのです。
持続的な事業成長には、人材の確保と育成、定着化が欠かせない要素となります。人事部門の役割は今後さらに重要性を増すでしょう。