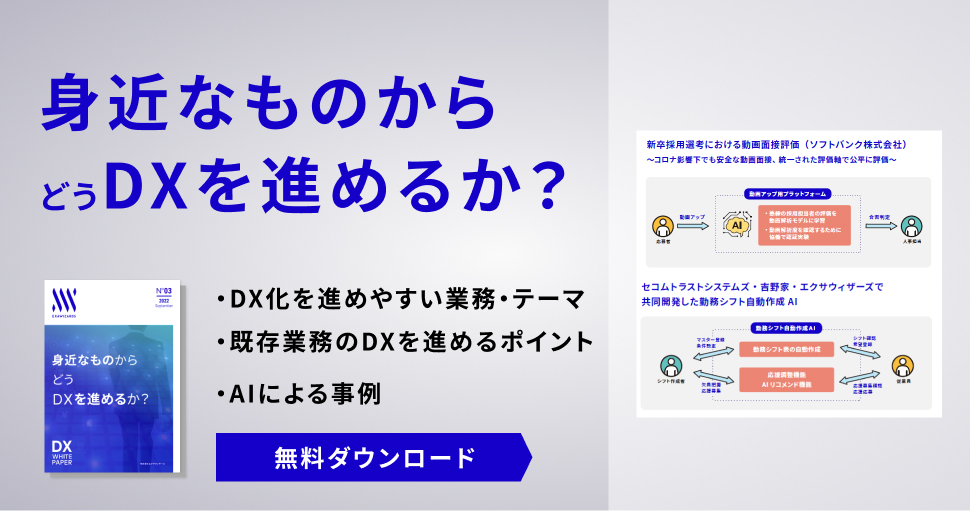デジタルトランスフォーメーション(DX)は、完全なIT導入ではなく、企業の競争力を高め、持続的な成長を実現するための経営変革です。DXを成功させるには、経営戦略への統合、組織文化の変革、適切なテクノロジーの活用、そしてDX人材の育成が重要となります。
企業がDXを推進する際は、業務のデジタル化にとどまらず、ビジネスモデルの変革や企業風土の改革にも踏み込む必要があります。
この記事では、DX推進の全体像を整理し、経営戦略から組織文化やテクノロジー、人材育成の重要性までを解説します。
<この記事の要約>
DX推進の全体像と成功戦略とは「戦略・組織文化・技術・人材の統合フレーム」
経営戦略へのDX統合、組織文化の変革、目的に沿った技術導入、人材育成の4軸をバランスよく強化することで、DXを企業変革として機能させる全体像を示す流れになる。
成功戦略1は「経営主導によるビジョン共有とガバナンス整備」になる
トップが明確なビジョンと方向性を示し、専任組織を設置し、PDCAサイクルを回すことで企業全体の一体的な改革推進が可能になる。
成功戦略2は「スモールスタートと組織文化の醸成」になる
実証プロジェクトから段階的に拡大しつつ、失敗を許容する文化とデータドリブン意思決定を根付かせることで、変革が現場に定着する組織への移行を実現する。
DX推進の必要性と背景
DXはIT化ではなく、ビジネスモデルや企業文化の変革を伴う経営課題です。ここでは、以下の観点で解説します。
- DXとは
- 2025年の崖と日本企業
DXとは
DXとは、企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して製品・サービスやビジネスモデルを変革するとともに、業務プロセスや組織、企業文化そのものを変革し競争上の優位性を確立することと定義されています。単なるIT化に留まらず、経営改革そのものを意味する広範な概念です。
参考:総務省「情報通信白書 デジタル・トランスメーションの定義」
2025年の崖と日本企業
日本企業では経済産業省の提唱した「2025年の崖」というキーワードも有名です。これは既存のレガシーシステムをこのまま使い続け、DXが進まなければ、2025年以降に最大で年間12兆円もの経済損失が生じる可能性があると警告したものです。まさにDX推進の遅れは企業存続に関わるリスクであり、今すぐに取り組むべき喫緊の経営課題といえるでしょう。
以下では、DX推進の全体像として戦略、組織文化、テクノロジー活用、人材育成の観点から解説し、具体的な日本企業の成功事例を紹介しながら、「結局、人材育成が鍵である」という結論に至るまでを解説していきます。
参考:経済産業省「DXレポート~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~」
DX推進の成功戦略1:経営戦略への統合とトップのコミットメント
デジタル技術の活用が企業の競争力を左右する時代、DX(デジタル・トランスフォーメーション)は単なるIT導入ではなく、経営戦略の一環として捉えることが求められています。トップのコミットメント が成功のカギを握り、経営層の明確なビジョンとリーダーシップがなければ、部門ごとの個別最適にとどまり、企業全体での変革は実現できません。
ここでは、以下の観点で解説します。
- DX成功の鍵は明確なビジョンと戦略
- トップのリーダーシップが重要
- DX推進の先進企業の取り組み
関連記事:DX戦略とは?成功させるための策定手順とポイントを徹底解説
DX銘柄に選出される企業が、どのような取り組みをおこなっているのかを知りたい方は、「2025年度のDX銘柄選定企業とは?選定されるメリットや今後の展望を解説」をご覧ください。
DX成功の鍵は明確なビジョンと戦略
DXを成功させるには、まず明確なビジョンと戦略が不可欠です。DXは企業全体を巻き込む変革であるため、経営戦略の中核に位置づけて推進する必要があります。
トップのリーダーシップが重要
具体的には、経営トップ自らが旗振り役となり、DXの目指す方向性(例えば「顧客体験の向上」「新規デジタル事業の創出」など)を社内外に明示しなくてはなりません。
- 顧客体験の向上(デジタル技術を活用したサービス改善)
- 新規デジタル事業の創出(DXを活用した新たなビジネスモデルの構築)
トップのリーダーシップのもと、各部門がバラバラにデジタル化を進めるのではなく、全社が一丸となって同じゴールに向かう「アラインメント(整合性)」を確保することが成功のポイントです。
DX推進の先進企業の取り組み
実際、経済産業省と東京証券取引所が選定する「DX銘柄」に選ばれるような先進企業は、DXを経営課題として位置づけ強力に推進しています。
例えば、DX推進指標という自己診断ツールを活用し、自社の成熟度を評価しながら、経営戦略に組み込んでいる企業が増えています。提出企業数は年々増加し、2023年には4,047社に達しました。
このように、DX戦略を経営戦略と一体化し、トップダウンで推進する体制構築がDX成功への第一歩です。
参照:IPA 独立行政法人 情報処理推進機構「DX推進指標 自己診断結果 分析レポート(2023年版) | 社会・産業のデジタル変革」
関連記事:2024年度のDX銘柄選定企業とは?選定されるメリットや今後の展望を解説
DX推進を成功させる、社内を動かす・うまく巻き込むコツとは?
DXを成功させるためには、社内を動かし、うまく巻き込むことが重要です。その中でも特に経営層を中心にアップダウン的に実施することで、DX人材の育成をより加速させることができます。
本資料では、DX推進・人材育成に不可欠な「経営層の巻き込み」について詳しく解説しています。ぜひダウンロードしてお役立てください。
\こんな方におすすめの資料です/
- DX人材育成の必要性は理解しているが、実際の推進が難しい
- 経営層の理解と協力が得られず、人材育成が進まない
- 全社的なDX推進のために経営層の協力が必要
- DX人材育成の取り組みを社内で加速させたい
- 経営層を巻き込んだDX推進の成功事例を知りたい
DX推進の成功戦略2:組織文化の変革と企業風土の再構築
技術を活用して競争力を高めるためには、従来の価値観や慣習を見直し、変化を受け入れる組織風土を醸成しなければなりません。 DX推進における企業文化の重要性と、変革を成功させるための具体的なポイントを理解しておきましょう。
- DX推進には組織文化の変革が必要
- 組織文化やがDX成功の妨げになるケースも
- 企業風土改革の具体的な取り組み
企業全体で、DXに向けた変革に取り組んでいく前に、「DX戦略とは?成功させるための策定手順とポイントを徹底解説」をぜひご覧ください。
DX推進には組織文化の変革が必要
社内でDXを推進するためには、全社でその目的が十分に共有され、一丸となって進めることが重要となります。単なるITプロジェクトとして捉えていると、一部署ではDX推進ができても横断的、全社的な展開でつまずくことも少なくありません。実際、PwCがおこなった「日本企業のDX推進実態調査2024(速報版)」によると、全社でDXに取り組むことが成果を大きく左右するという結果がでています。そのため、真のDX推進には組織文化(企業風土)の変革を行い、従来のやり方や価値観を見直し、変化を受容する企業文化を育む必要があります。
参考:PwC「日本企業のDX推進実態調査2024(速報版)」
組織文化や慣習がDX成功の妨げになるケースも
企業の文化や価値観、慣習は、新技術の導入・活用を進める際に大きな影響を与えるため、ここを改革しなければデジタル化の効果も限定的です。例えば、日本企業では長年培われた縦割り体制や対面重視の風土がある場合、DX推進の妨げになる可能性もあります。そのため、経営層を中心にデジタル技術の導入と並行して組織風土改革に着手する必要があると指摘されています。
企業風土改革の具体的な取り組み
組織文化の変革を実現するためには、以下のような取り組みが効果的です。
- 失敗を許容しチャレンジを推奨する風土づくり:社員が積極的に新しい試みに挑戦できる環境を整える。
- データドリブン文化の浸透:直感ではなく、データに基づいた意思決定を行って文化を確立させる。
- 部門間の壁を越えたコラボレーション促進:部門間の連携を強化し、組織全体でDXを推進する。
「DXの本質は企業文化の変革にある」とも言われるように、人と組織のマインドセットをアップデートし続けることが、DX推進の基盤を整えるのです。
DX推進を成功させる、社内を動かす・うまく巻き込むコツとは?
組織的にDXを推進し、事業変革を進めるためには「社内をうまく巻き込んでいく」ことが重要となります。
しかし、思ったように社内の協力を得られず、DXが進まないと悩んでいる担当者は少なくないものです。
本資料では、「DX推進における社内巻き込みの重要性」、「巻き込みを成功させる3つのポイント」など、全社的なDX推進に必要となってくる「社内の巻き込み」にご紹介していますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。
\こんな方におすすめの資料です/
- DX推進に他部署の協力が得られない
- 一部のDXではなく全社的なDXを推進したい
DX推進の成功戦略3:テクノロジー活用〜目的に沿ったデジタル技術導入〜
DXを推進する際、AIやIoT、クラウドなどの最新技術に注目が集まります。ただし、重要なのはテクノロジーそのものではなく、それをどのように活用し、企業価値を高めるかという視点です。
- DX推進におけるテクノロジーの役割
- 守りのDXから攻めのDXへ
- データ活用による競争力の強化
DX推進におけるテクノロジーの役割
DX推進ではAI、IoT、クラウド、ビッグデータ、RPAなど様々なデジタル技術がキーワードになります。しかし、重要なのはテクノロジーそのものではなく、それをどう活用して新たな価値を生み出すかです。
守りのDXから攻めのDXへ
先進企業の事例を見ると、単なる業務効率化(守りのDX)に留まらず、デジタル技術をてこに新規サービスやビジネスモデルを創出する攻めのDXに挑戦しています。例えば、あるメーカーでは製品にIoTセンサーを組み込み、稼働データを分析して予防保全サービスという新たな付加価値ビジネスを展開しています。
データ活用による競争力の強化
多くの企業が注力しているのがデータの徹底活用です。自社のデータを資産と捉え、AIで解析して意思決定やサービス改善に活かすことで競争優位の源泉としています。さらにオープンイノベーションや異業種企業との協業によって、自社に不足するデジタル技術や発想を取り入れ、変革のスピードを加速させている企業も少なくありません。
このように、自社の目的(ビジョン)に沿って最適なテクノロジーを選択・導入し、新たな価値創造につなげることが重要です。技術導入はゴールではなく手段であることを忘れず、ビジネス目標に直結する形でデジタル活用を進めましょう。
DX人材育成の重要性について
DX推進の成功を左右する最大の要因は「人材」です。最新技術や戦略が整っていても、それを活用し、変革を推進できる人材がいなければ意味がありません。しかし、日本企業では慢性的なDX人材不足が課題となっています。
以下のポイントを見ていきましょう。
- 日本企業におけるDX人材不足の現状
- DX人材確保のための解決策
日本企業におけるDX人材不足の現状
日本ではDX人材の不足が深刻化しており、2030年には最大で約79万人ものデジタル人材が不足するという予測もあります。
また、IPAの「DX動向2024」によれば、企業がDXを推進できない理由のトップは「人材不足」(60%以上の企業が回答)で、他の要因を大きく引き離しています。このように、人材確保の遅れがDX推進の大きな障壁となっているのが現状です。
参照:IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)DX動向2024 DXの取組状況(経年変化および米国との比較)
DX人材確保のための解決策
DX人材不足を解消するため、各社ではリスキリング(学び直し)に取り組んでいます。
DXを実現するのも推進するのも“人”であり、人材育成こそがDX成功の鍵であることを肝に銘じる必要があります。
DXの人材を確保するには、人材育成の手法を知っておく必要があります。詳しくは、「DX人材育成の方法を大公開|育成の課題・メリット・手法を徹底解説!」を参考にしてください。
DX人材育成における、ROIの考え方・ポイントを大解剖
DX投資、人材育成は目的や投資対効果の考え方が異なります。
では、DX人材の育成に取り組む上でROIとどのように向き合うのが適切なのでしょうか。
本資料は、DX推進担当者向けに、DX人材育成を推進する上で重要な考え方3つをお伝えします。
DX人材育成の育成計画や目標を策定する際の参考としてお役立ていただけますと幸いです。
\こんな方におすすめの資料です/
- 人材育成におけるROIとの向き合い方がわからない
- 役員陣に対して、費用対効果の説明がうまくできない

企業におけるDX推進の成功事例
ここで、実際にDXを推進し成果を上げている日本の大企業の成功事例をいくつか紹介します。どの企業も試行錯誤の末にDXを軌道に乗せ、大きな効果を実現しています。
ここで紹介した以外の企業が、どのようにDXを進めているのか知りたい方は、「【2024年最新版】DX事例集|国内外・自治体や中小企業まで自社に合ったDXの成功事例を見つけよう」をご覧ください。
事例①:ユニクロ(ファーストリテイリング)のDX戦略
ファーストリテイリングが展開するユニクロは、アパレル業界でいち早くDXを進めた企業の一つです。同社はRFIDタグ(無線ICタグ)を活用した在庫管理と無人レジの導入で知られています。
店舗の商品にRFIDタグを取り付け、レジではお客が商品を専用機器に置くだけで複数商品を一括スキャン可能なセルフレジを実現しました。ユニクロやGUではこのRFIDによる無人レジ化により、バーコードを個別に読み取る必要なく商品を認識でき、レジ待ち時間の大幅短縮を実現しています。
RFIDによりリアルタイムに在庫情報を収集して本部で分析することで、適切な商品補充や在庫圧縮をデータに基づき行えるようになりました。DXの成果として顧客の購買体験向上(レジ待ち解消)と供給チェーン効率化の両立を果たし、同社の売上・在庫回転率向上に貢献しています。
さらに、ユニクロは「情報製造小売業」というビジョンを掲げ、顧客データに基づいた商品の企画・製造・販売の一気通貫体制を構築する有明プロジェクトも推進しています。店舗とECの融合やAIによる需要予測などDX戦略を全社で展開中です。
大きな権限を持つ柳井正自らがDXの必要性を唱え陣頭指揮を取ったことが、この変革を成功させた要因と言えるでしょう。
参照:ユニクロ「サプライチェーン改革について|2018年8月期決算」
事例②:ローソンのDX(無人店舗・業務改革)
コンビニ大手のローソンも業界をリードするDX推進企業です。ローソンは2020年、富士通と協働して実証実験店舗「ローソンゴー(Lawson Go)」を新川崎に開設した取り組みをはじめ、2025年春にReal×Tech Convenienceの仕組みを構築するための実証実験をさらに拡大しています。
この店舗での取り組みはカメラとAIによる無人決済システムを導入し、来店客はスマホアプリか顔認証・静脈認証で入店登録を行います。店内で商品を手に取ると、天井設置のAIカメラがその商品と数量を自動認識し、顧客が店を出ると連携したアプリに電子レシートと請求が届く仕組みです。
これによりレジ精算のための人手が不要となり、店舗スタッフの労働時間は通常店舗の4分の1にまで削減、人件費の大幅削減を実現しました。省人化によるコスト削減だけでなく、消費者にとってもレジ待ち不要で買い物時間の短縮というメリットがあり、顧客体験の向上につながっています。
さらに、2025年春に予定している高輪での実証実験では「ロボット活用による店舗業務の最適化」や「次世代のリモート接客ブースの設置」などを追加して行うことが予定されています。例えば、これまで人が行っていた品出しや店内清掃、商品配送などでロボットを活用することがあげられます。
また、リモート接客では専門スタッフが通信や電気・ガスなど、生活インフラに関する相談に対応できるようにしたり、将来的にはAIを活用した対応も予定しています。最初の実証実験から、技術が進展したことでテクノロジーの活用範囲が拡大し、現場業務の自動化・効率化が進むと期待されています。
参照:LOWSON「常に業界の先陣を切りつつ 新たなイノベーションに取り組み続けています」
LOWSOM「三菱商事・KDDI・ローソン、「未来のコンビニ」への変革に向けた取り組みを開始」
事例③:コマツのDX(スマートコンストラクション)
製造業・建設業界でもDXの波が押し寄せています。その代表例が大手建機メーカーのコマツです。同社はIoTとAIを搭載したスマート建機ソリューションを提供し、自らの事業モデルも変革しています。建設機械にセンサーや通信機器を取り付け、稼働状況や位置情報をリアルタイムで収集する「KOMTRAX(コムトラックス)」というIoTシステムを早期に開発しました。
そのデータを活用し、遠隔から機械の稼働を一元管理できるサービスや、AIで部品劣化を検知して故障予兆を知らせる予知保全システムを顧客企業向けに提供しています。これにより建設現場では、機械の稼働率向上や最適なメンテナンス時期の把握、生産性向上が実現しました。
実際ある顧客企業では、KOMTRAX導入により設備稼働率が向上し生産性が140%も増加する大幅な改善効果が報告されています。また、コマツは自動運転や遠隔操作が可能なICT建機も開発し、熟練オペレーター不足に対応するソリューションも提供しています。
これらの取り組みにより、単なる建機メーカーからデータサービス企業へとビジネスモデルを転換しつつあります。
製品(ハード)+データ(ソフト)の提供によって顧客の生産性向上に貢献し、新たな収益源を得ている点がDX成功の好例です。背景には、建設業界の人手不足や生産性向上ニーズという課題があり、コマツはそれをデジタル技術で解決する戦略を描いたと言えます。
参照:コマツ「目指す未来の現場に向けて|コマツについて」
事例④:KDDIのDX人材育成(社内大学による人材戦略)
DX成功の鍵が人材育成であることを示す好例として、通信大手KDDIの取り組みが挙げられます。同社はDXを事業戦略の柱に据え、社員のDXスキル向上のため社内大学「KDDI DX University (KDU)」を2020年に設立しました。
KDUでは、データサイエンスやAI、ビジネスデザインなどDX推進に必要な知識・スキルを習得する研修プログラムを体系立てて提供しています。特徴的なのは研修の専門性と徹底度で、DX人材育成に特化した高品質な研修カリキュラムを用意し、選抜メンバーに年間200時間以上の学習機会を与えている点です。
受講者は社内の実プロジェクトでOJTを通じて学んだ内容を実践し、DX推進の即戦力となることが期待されています。KDDIはこの社内大学を通じて自社に数百人規模のDX人材プールを創出することを目指しており、日本企業では類を見ないユニークな試みと評価されています。
さらに、育成だけでなく社内でのDX人材のキャリアパス整備や評価制度の見直しも進め、育てた人材が社内で活躍・定着できる環境づくりにも注力しています。
KDDIの事例は、単発の研修ではなく経営戦略に紐づいた継続的な人材育成の仕組みを作ることで、人材不足というDX推進上の課題に挑戦している点で他社のモデルケースとなっているのです。
参照:KDDI「求む!未来のDX人財 「KDDI DX University」を設立したKDDIのDXに懸ける本気度」
事例⑤:イオンが実施したデジタル人材の育成・発掘
イオン株式会社は、中期経営計画の成長戦略に「デジタルシフトの加速と進化」を掲げており、デジタル人材の育成、また適性のある人材の発掘し、社内の共通デジタル基盤を整備することを実現しています。
中長期的なDX推進を行ううえでデジタル人材の量・質に着目した同社は、デジタル人材の育成や発掘が急務となっていました。特に従業員の中でもどのようなスキルがあるのか、また適性を可視化する必要がありました。
そこで、エクサウィザーズが提供するDXアセスメント(DIA3.0)を約7,000名が受検し、DXに関する知識量が多くなくても、マインド・スタンスに適性がある人材の発掘ができるようになりました。
そのうえで、適性のある人材の育成をイオングループ内の企業内大学イオンビジネススクールで実施し、発掘から育成につなげるというデジタル人材開発を実現した事例となります。
関連記事:「デジタルシフトの加速と進化」を支える人材発掘に向けて、約7,000名でDXアセスメントを受検。
DX推進を成功させるポイントとステップ
上記のような事例から見えてくるように、DX推進を成功させるためにはいくつか共通するポイントがあります。ここではDX推進のためのガイド要素として、企業が押さえるべきポイントを整理します。
- 経営ビジョンの明確化と共有
- 経営戦略への組み込み
- 専任組織・リーダーの設置
- 人材育成と組織風土の醸成
- スモールスタートとアジャイルな実行
- データ活用とIT基盤整備
経営ビジョンの明確化と共有
DXによって何を実現したいのか、経営トップが明確なビジョンを示し、それを社内に浸透させます。
DXは単なるIT導入ではなく経営改革であるため、ゴール(例えば「〇〇業界で顧客満足度No.1のデジタル企業になる」等)を定義し、全社員がそれを理解・共感することが出発点です。
経営戦略への組み込み
DXを経営計画や中期計画の中核に据え、具体的な戦略・KPIを設定します。DX推進は企業一丸で取り組むべき課題であり、経営戦略に組み込まなくてはなりません。
例えば、新規事業創出の数値目標や業務効率○%改善など、DXによる目標を経営指標として定めます。トップ自らが進捗をモニタリングし、必要なリソース(予算・人員)を配分することも重要です。
専任組織・リーダーの設置
全社横断でDXを推進する専任組織(CDO直属のDX推進部門など)やプロジェクトチームを設置します。各部門からメンバーを集めた横串の組織とし、サイロ化を防ぎます。
リーダーにはビジネスとITの両方に通じた人材を据え、権限と責任を明確にしましょう。
スモールスタートとアジャイルな実行
DXは一朝一夕に完成するものではありません。まずは効果が測定しやすい領域から小さく始め、成功体験を積み重ねることが大切です。
例えば特定の業務プロセスのRPA導入や、一店舗での実証実験などから着手し、成果と課題をフィードバックしながら段階的にスケールアップします。変化の速いデジタル時代には計画の見直しも機動的に行い、アジャイル的な推進体制を敷くとよいでしょう。
データ活用とIT基盤整備
DXの土台となるデータ基盤やシステムアーキテクチャを整備します。データが社内で散在・サイロ化していては活用もままなりません。クラウド活用やデータレイクの構築などによりデータを統合・利活用できる環境を構築します。
また、老朽化したレガシーシステムの刷新も避けて通れません。技術的負債を解消し、将来を見据えたモダンなITインフラへ移行することで、新技術の導入もスムーズになります。経済産業省のDXレポートでも指摘された「レガシー刷新の遅れ」がDXの足かせにならないよう、思い切った投資判断も必要です。
人材育成と組織風土の醸成
結局、DXを動かすのは「人」です。社員のデジタルリテラシー向上やスキル習得のための教育プログラムを用意しましょう。社内勉強会・研修、eラーニング、外部講座受講支援、社内公募によるプロジェクト参加機会など、複数の施策を組み合わせて継続的に人材育成に取り組みます。
また、学んだことを現場で実践し定着させる仕組み(OJTやジョブローテーション)も重要です。同時に、「失敗を恐れず挑戦する」文化や「データに基づき意思決定する」文化への転換を図りましょう。
現場の一人ひとりがDXの当事者としてアイデアを出し合い行動できるようになることで、DX推進は強力な推進力を得ます。
以上のポイントを踏まえつつ、自社の状況に合わせたロードマップを描くことが有効です。
特に中堅・中小企業ではリソースが限られるため、焦点を絞った施策展開と外部支援の活用(専門コンサルやベンダーとの連携)も検討すると良いでしょう。重要なのは、部分最適に終わらず全体最適の視点でDXを捉えること、そして短期の成果と中長期のビジョンを両立させることです。
まとめ
DX推進の全体像として、戦略・文化・技術・人材の側面から解説してきましたが、最後に改めて強調したいのは「結局、人材育成が鍵である」という点です。戦略を立てるのも、新しい技術を使いこなすのも、組織文化を変えていくのも、すべて現場で動く「人」が担うものです。DXは、究極的には人材開発のプロジェクトとも言い換えられます。
日本企業の成功事例でも、デジタル人材の育成と確保を両輪で進めてDX推進体制を強化していることが共通点として浮かび上がります。企業は学習する組織へと進化し、社員の成長を支える環境を整えることが成功の第一歩となるでしょう。
なお、なかなかDXのイメージがわかない場合は、身近な業務のDX化を知ることから始めてみてはいかがでしょうか。以下の資料では、DXが進めやすい業務や導入する方法をまとめているため、ぜひご確認ください。