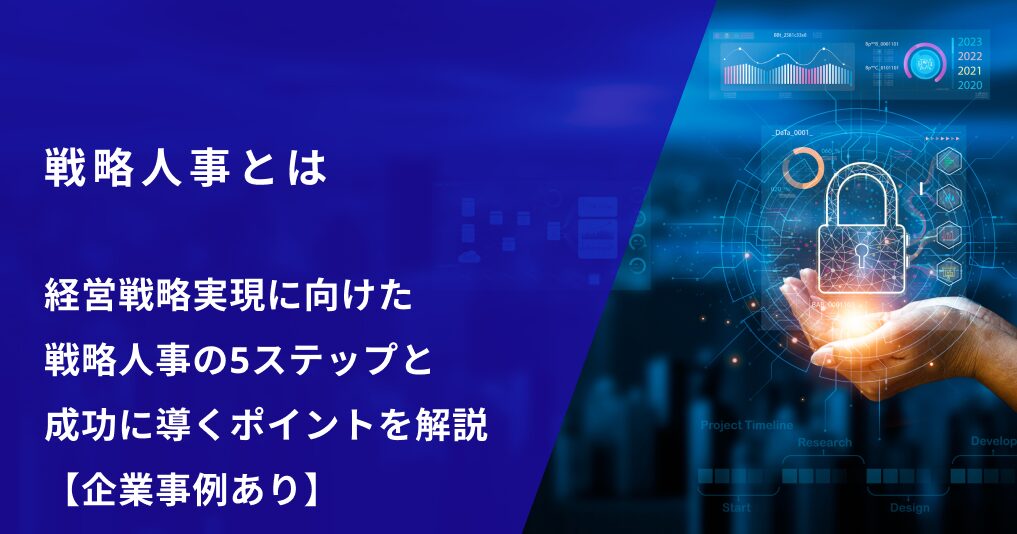戦略人事とは、経営戦略実現のために人材を戦略的に活用する施策を指します。国際情勢や社会構造の変化に対応し、企業が持続的な発展を遂げるためには、人的資源を最大限活用することが求められます。
この記事では、経営戦略実現に向けた戦略人事の重要性を解説し、戦略人事実施のステップと成功に導くポイントを紹介します。
戦略人事とは
戦略人事とは、経営戦略の実現に向け、人的資源を戦略的に活用する取り組みを指します。経営資源のひとつである「人材」を最大限活用し、経営戦略と連動した人事施策を立案・実行して、収益向上により企業運営に貢献を果たすものです。
戦略人事は「戦略的人的資源管理(Strategic Human Resources Management)」とも呼ばれ、頭文字をとって「SHRM」と表記することもあります。いずれも、経営戦略の実現に向け、人的資源を活かした施策を実行することを指します。
ウルリッチ氏が提唱した戦略人事の概念
戦略人事の概念を最初に提唱したのは、米国ミシガン大学教授のデイビッド・ウルリッチ氏です。1990年に著書「MBAの人材戦略」のなかで、「HRBPモデル」として人事の役割を以下の4つに分類しています。
| 戦略的パートナー | 経営戦略・事業戦略をもとに人事施策を立案・構築 |
|---|---|
| 管理のエキスパート | 策定された人事施策を運用 |
| 従業員のチャンピオン | 従業員の声を聞き意見集約と対応 |
| 変革のエージェント | 組織全体の変革をリード |
これまで多くの人事部門は、法律や社内規程の枠組みのもと、定型的な管理業務に従事するのが中心的な業務でした。これに対しウルリッチ氏は、人事部門は人事施策によって積極的に経営に関与し、経営戦略実現に向けコミットすべきと主張しています。
戦略人事と人事戦略の違い
「戦略人事」とよく似ており混同しやすい用語に「人事戦略」があります。ウルリッチ氏の主張の通り、戦略人事はより経営に深く関わるものであるのに対し、人事戦略は人事業務の範疇における改善活動を指すものです。
例えば、人事戦略は採用や育成、評価制度の運用や人材の定着施策といった人事業務を改善する取り組みです。組織の生産性を高める施策であり、経営戦略に間接的に影響を及ぼします。これに対し戦略人事は経営戦略が前提にあり、その実現のため直接的に人的領域に関する施策を提案・実行することを指します。
戦略人事が求められる背景
企業が存続し成長を続けていくには、人材をどれだけ有効に活用できるかにかかっているといっても過言ではありません。ここでは、戦略人事が求められる背景について整理していきましょう。
- ビジネス環境の変化
- ESGやサスティナビリティへの対応
- 人的資本経営への注目度の高まり
ビジネス環境の変化
IT技術の進歩が目覚ましいDXの進展やAIの活用などにより、多くの企業は新たなデジタルを活用した変革を迫られています。加えて、経済の低迷や人口減少による国内需要の減少や人手不足の問題なども拍車をかけ、事業を継続していくには戦略性の高い対策が必要になります。
また、働き方も多様化や従来の日本的雇用の崩壊など、人材を取り巻く環境も大きく変化しています。こうした変化に対応するには、人事領域を所管する人事部が、積極的に経営に参画することが求められるようになったのです。
ESGやサスティナビリティへの対応
近年、企業には多くのことが求められるようになりました。特に環境面への配慮や社会への貢献は、企業価値を測る指標とされています。こうした風潮の高まりにより、持続可能な活動を追求するサスティナビリティや、長期的な成長のために、環境・社会・ガバナンスに配慮するESGの重要性が高まりました。
人材領域についてもダイバーシティに代表されるように、さまざまな背景を持つ人材の活躍を推進していくことが求められます。こうしたなか、人事部門は中長期的な視点を持ち、企業の発展のために人事面の取り組みで、積極的に経営に関与することが求められるのです。
人的資本経営への注目度の高まり
海外では早くから人的資本という概念に注目が集まっていましたが、日本国内でも2020年の「人材版伊藤レポート」の発表により、人的資本経営への関心が一気に高まりました。人的資本経営とは、人材を「資本」ととらえ、中長期的な企業価値向上に役立てていく経営のあり方を指します。
人的資本経営で掲げられた一番のポイントがまさしく「経営戦略と人事戦略の連動」であり、これを実現するために、人事部門のあり方も大きな変革が必要となったのです。
戦略人事のメリット
戦略人事のメリットは経営戦略と人的マネジメントの連動性が高まることです。これにより人的リソースを活用する経営施策を、タイムリーに実施できるようになります。
従来の人事は経営層との距離があり、経営戦略に関する意思決定にダイレクトに関わることは稀でした。こうした状況では人的施策と経営戦略の間にタイムラグが生じ、さまざまな問題や環境変化への対応スピードが損なわれるリスクがあります。戦略人事により、こうしたリスクの回避が期待できる点はメリットです。
組織風土の醸成や従業員の意識変革などの人事施策は一般的に時間がかかるものですが、経営戦略と連動することにより早期に結果につなげていきやすくなるのです。
戦略人事の例
ここでは戦略人事における人材マネジメントの例を見ていきましょう。採用・育成・配置・評価・処遇の側面から、取り組み例を挙げます。
| 施策 | 概要 | |
|---|---|---|
| 採用 | ダイレクトリクルーティング | 企業側から積極的に人材にアプローチして採用につなげる手法。経営戦略実現のために必要なスキルを持った人材をピンポイントで採用する。 |
| 育成 | リカレント教育 | 従業員個人が仕事で必要な知識やスキルをアップデートできるように、企業内大学の設置や高等教育機関での学び直しの機会を提供する。 |
| 配置 | タレントマネジメント | 個々の従業員のスキルや特性を可視化することにより人材配置を最適化する。環境変化による戦略の変更にも柔軟に対応できるようになる。 |
| 評価 | OKR(Objectives and Key Results) | 組織目標と達成のために必要な成果を結びつけ、企業の方向性を明確にする目標設定・管理の手法。経営戦略実現に向けた、行動を引き出していく評価手法。 |
| 処遇 | 定年延長 | 高スキルのベテラン社員の活用促進のため、定年年齢を延長する。モチベーション維持のため、役職を外れた後も活躍できる役割の設定や、処遇の改善などが求められる。 |
経営戦略の実現に向けて必要な人材を明確化し採用することや、既存人材に必要スキルを習得してもらう機会を用意すること、マンパワーを最大化するための人材配置の工夫など、こうした取り組みが戦略人事の例として挙げられます。
戦略人事に必要な4つの機能・役割
ここでは、戦略人事を進めるにあたって、必要な機能や役割を解説します。
戦略人事の提唱者であるウルリッチ氏が掲げた「HRBPモデル」をもとに、現在では戦略人事を担う組織として必要な機能・役割として以下の4つが定着しています。
- HRビジネスパートナー(HRBP)
- センター・オブ・エクセレンス(CoE)
- オペレーション部門
- 組織開発・人材開発(OD・TD)
HRビジネスパートナー(HRBP)
HRビジネスパートナーとは、人事部門(HR)と経営層や現場のリーダー(BP)との連携強化・協働を推進する機能です。効果的に戦略を実行していくには、経営層の考えを深く理解することと、現場の実態やニーズを正確に把握することが欠かせません。ビジネスパートナーとのコミュニケーションを密におこない、経営戦略の一翼を担っていく役割です。
センター・オブ・エクセレンス(CoE)
センター・オブ・エクセレンス(CoE)とは、人実施策における優秀なブレーンとしての役割です。人的マネジメントにおける専門知識と高度なスキルを有し、経営層にその知見を提供し、戦略人事実行のサポートを担います。採用・育成・配置・処遇などの幅広い知見が必要で、それぞれを熟知した経験豊富な人材が求められます。
オペレーション部門(OPs)
オペレーション部門とは、人事関連の実務の実行部隊を指します。CoEで策定された人事施策を日々運用する機能です。具体的には、給与計算や勤怠管理・社会保険業務、人事異動の手続きや採用プロセスの運用などが挙げられます。従来の人事部としての基本機能であり、正確性と効率的な運用が求められる役割です。
組織開発・人材開発(OD・TD)
組織開発(Organization Development)とは、戦略実行のための組織体制を作りあげる機能を指します。経営戦略実現に向けた課題を抽出し、人材と組織の相互作用をもたらす体制を構築し課題の解決を図ります。
人材開発(Talent Development)とは、経営戦略実現に向け個々の人材の能力を引き出す、教育研修の機能です。個々の従業員のスキル向上やマインドの醸成にスポットをあて、課題解決に寄与できる人材を育成します。
組織開発と人材開発は戦略人事における両輪であり、バランスよく効果的に機能することが求められます。
人事戦略策定について詳しく知りたい方は、「人事戦略策定のポイントとは|策定のステップと有効なフレームワークを紹介【企業事例あり】」をご覧ください。
戦略人事実施の5ステップ
ここでは、戦略人事を実行する際の5ステップを解説します。
- 経営ビジョン・経営戦略の理解
- 経営戦略に基づいた人材ビジョンの策定
- 中長期経営計画の理解
- 中長期人事計画の策定
- 採用・育成計画の策定と具体化
戦略人事実行のステップは、経営ビジョン・経営戦略を、実務レベルに落とし込んでいく作業ともいえるでしょう。
経営ビジョン・経営戦略の理解
戦略人事では、まず経営ビジョン・経営戦略を深く理解することからはじめなくてはいけません。経営戦略の実現が戦略人事の目的です。そのため、経営戦略が明確でなかったり、理解に齟齬が生じていたりした場合は、戦略人事に基づく施策が的外れなものになるばかりではなく、事業運営にマイナスの影響を及ぼします。人事部門と経営層が連携を深め、協働することにより、経営ビジョンと経営戦略を共通認識としましょう。
経営戦略に基づいた人材ビジョンの策定
経営戦略の内容を十分に理解したうえで実現したときに、自社の人材構成がどのような状態になっているべきか、あるべき姿としての人材ビジョンの策定をおこないます。目標を達成するには、どのようなスキルを持った人材がどれくらい必要なのか、あるいは共通して持っておくべきマインドなどを具体的に策定します。
中長期経営計画の理解
企業は経営戦略をもとに、3年単位あるいは5年単位など中期的な目標を設定し、実現のための計画を策定します。この中期目標を確実に理解したうえで、人事部門としてなすべきことを明確化していきます。加えて、長期的な経営計画も把握して、将来に向け備えておくべきことも理解しておきましょう。
中長期人事計画の策定
中期経営計画の達成に向け必要な人事施策を洗い出し、中期人事計画を策定します。例えば、目標達成に必要とされるであろう採用人数と人材要件を明確にし、中長期的な視点で採用計画に落としこむといった作業になります。中長期的な経営目標から逆算し、必要な人事施策を明確にして実行計画を立てることは、経営戦略実現に向けた重要な取り組みです。
採用・育成計画の策定と具体化
策定した中長期人事計画をもとに、より具体的な採用計画と育成計画に落とし込む作業です。採用であれば直近で採用すべき人数と人材要件を確定し、実施スケジュールを立てます。育成については経営戦略実現に向け、誰がどのようなスキルを身に着けるべきか明確にし、研修等の教育施策をスケジューリングします。そしてそれぞれ担当者が、スケジュールに沿って具体的にアクションを起こしていくプロセスです。
人的資本のデータ活用については、「人的資本を最大化するスキルデータ活用ガイド ~企業の競争力を高める戦略的人材マネジメント~」もご覧ください。
戦略人事を成功させるポイント
戦略人事を成功に導くには、いくつかのポイントを押さえたアクションが必要です。以下、5つのポイントを解説します。
- 外部環境を適切に把握する
- 経営戦略を明確化し共通認識とする
- 従業員の信頼を得る
- 成果指標を明確にする
- 適切に外部リソースを活用する
外部環境を適切に把握する
戦略人事においては、人事部門にも経営的視点が求められます。そのため、人事領域の知見だけではなく、自社を取り巻く業界動向や、そのなかでの自社の立ち位置など、外部環境にも目を向ける必要があります。
将来的に脅威あるいは追い風となりうる市場動向なども、適切に把握しておかなくてはなりません。戦略人事に取り組む際は自社の内部だけでなく、国際情勢まで含めた広い視野で戦略を組み立てる必要があるのです。
経営戦略を明確化し共通認識とする
経営層と人事部門で経営戦略を共通認識とすることが、戦略人事の実行において最も欠かせないことは前述したとおりです。根幹となる経営戦略が曖昧であれば、効果的な人事施策が打てず戦略人事は機能しません。
また、当初は共通認識であっても、状況の変化により経営戦略を軌道修正することもあります。そのときに経営層と人事部門の一体性が失われていては、タイムリーな微調整ができなくなります。経営と人事は、常に密接に連携しておくことが、効果的な戦略人事に欠かせないことなのです。
従業員の信頼を得る
戦略人事において、人事部門は現場と経営の橋渡し的な役割を担うことも期待されます。理想的な経営戦略が掲げられていたとしても、現場で働く多くの従業員の置かれた状況とあまりに乖離していれば、会社に対する不信感につながるためです。
人事部門は、積極的にコミュニケーションをとり、現場の状況を経営層に伝えなくてはなりません。また反対に従業員に対して、経営の考えをかみ砕いて説明することも必要です。こうした役割を担うには、従業員からの信頼が必要になります。
成果指標を明確にする
戦略人事を実行するにあたって、取り組むべき人事施策の成果指標を定めることも必要です。従業員の理解を得るためにも、分かりやすい形で定めることが望ましいでしょう。成果を曖昧にせずタイムリーに検証することで、経営・人事・従業員の間の共通認識に基づいた活動ができているかを確認できます。
経営戦略実現に向けた人員の充足数など、定量的に設定できるものは必ず数値で示します。従業員のスキル向上の状況や、従業員満足度など定性的な指標についても、サーベイを実施するなどして、客観的に検証する体制を構築しましょう。
適切に外部リソースを活用する
戦略人事を実行するにあたり、すべてのリソースを社内で調達することは現実的ではありません。例えば成果を検証するための定期的なサーベイは、外部サービスを利用することにより客観性を担保できます。
またタレントマネジメントなどの人材管理ツールも内製化した場合、システムの開発に多くのコストと時間を費やします。こうしたツールは自社の現状に合った外部サービスを利用することで、早期の導入が可能になりメンテナンス等の手間も省けるメリットがあります。
DX人材育成について詳しく知りたい方は、「DX人材育成の方法を大公開|育成の課題・メリット・手法を徹底解説!」をご覧ください。
成果を上げた戦略人事の好事例
ここでは、各業界で成果を上げた、以下3社の戦略人事の好事例を紹介します。
- 日清株式会社
- 楽天グループ
- 中外製薬株式会社
- サッポロホールディングス株式会社
日清株式会社
日清グループでは「人材が企業価値の源泉である」というポリシーが創業以来根付いています。そのポリシーを具現化した戦略人事が「NISSIN ACADEMY」に代表される人材育成の取り組みです。NISSIN ACADEMYは、会社の未来を担う人材を育てること、健全な社内競争により社員が切磋琢磨することを目的に、従業員の学びの場として設立されました。
企業内大学のような位置づけで、希望する社員すべてが自発的に参加できる「公開型プログラム」と、将来の経営層や事業をリードする人材を育成する「選抜型プログラム」の2本柱で構成されています。
公開型プログラムでは、会社理解や業務に関する汎用スキル向上を目的としたカリキュラムが用意されています。「選抜型プログラム」では、希望者のなかから対象者を選抜し、ワークショップやビジネススクールでの学びを通じて、各領域の専門スキルやビジネスリーダーとしての資質を養う環境が用意されています。
楽天グループ
楽天グループでは、「イノベーションを通じて、人々と社会をエンパワーメントする」というミッションの実現に向けて、さまざまな戦略人事に取り組んでいます。2017年に「採用」「育成」「定着」の3つを柱とした、「Back to Basics Project」と銘打ったプロジェクトを掲げ、「勝てる人材、勝てるチーム」による強固な人材基盤の構築に取り組んできました。
また、楽天グループでは人材管理にピープルアナリティクスの手法を取り入れています。同社のデータに基づいた意思決定を重視する社風から、人材マネジメントにおいてもデータドリブンな取り組みがなされています。
ピープルアナリティクスとは、社員の属性データや行動データを分析し、採用活動や人材配置をはじめ、従業員満足度の向上など、さまざまな人事施策にデータによる意思決定を反映する手法です。同社ではピープルアナリティクスを要員計画に活用することで、精度の高いチームごとの人員目標の達成度の予測や、ジョブローテーションの検討、階層別の教育施策の実施を可能にしています。
中外製薬株式会社
中外製薬株式会社では、成長に向けた経営戦略として「TOP I 2030」を掲げ、さまざまな戦略人事に取り組んでいます。提携先であるロシュ社との人材交流プログラムや、会社に籍を置きながら新興国のNPOに参加して課題解決を図る「留職プログラム」など、さまざまな施策を講じてきました。
さらなる成長に向け、経営戦略遂行に必要な次世代リーダーやコア人材の育成の仕組み構築を目的とした、タレントマネジメントシステムとサクセッションプランの策定に取り組んでいます。
- 個々人の能力と適性に応じた人材育成プランの策定と実践
- タレントプールシステムの構築と運用
- サクセッションプランの策定と実行
上記3つをゴールとして策定され、将来の幹部候補となる人材群の母集団形成や育成に向けた仕組みづくりに取り組み、2011年以降延べ700名を超える後継者人材の選抜という成果を上げています。
サッポロホールディングス株式会社
サッポロホールディングス株式会社では、リカレント教育の一環としてDXリテラシー向上に向けた、全社員4000人を対象としたeラーニングを導入しています。同社では、急激なデジタル化に対応する人材の枯渇という課題を抱えており、デジタル化による本質的な改革を推進できる人材の育成に取り組みました。
ホールディングス主導のもと、まず社内のDXリテラシー向上のため、エクサウィザーズ社の「exaBase DXアセスメント&ラーニング」を導入します。導入の決め手となったのは、アセスメントと育成がセットで体系化されており、トータルでDX人材の育成が図れる点でした。全社員4000人に実施したeラーニングコンテンツの評価が高く受講が進んだことにより、社内においてDXに対する共通認識の醸成が一気に進みました。
将来を見据えたDX推進のサポーター・リーダーステージの人材募集に対し、定員を超える応募が集まるなど、導入当初の想定を超えた効果が現れています。
参考:お客様の声「サッポロホールディングス株式会社」(エクサウィザーズ)
DX人材の育成を科学的に支援する「exaBase DXアセスメント&ラーニング」なら、スキル可視化と個別最適な学習機会を一体で提供します。アセスメントで現状を診断し、レベルに応じた研修カリキュラムを自動で提案。人事・現場双方に負担をかけず、組織のDX推進を加速させます。
ピープルアナリティクスの活用に興味がある方は、「ピープルアナリティクスとは|データドリブンな人事施策が求められる背景と進め方を解説」をご覧ください。
まとめ
企業を取り巻く環境が激変するなか、持続的な成長を続けるには優れた経営戦略が必要となります。経営戦略の推進を支えるのは人材であり、人材への取り組みが企業の将来を左右するといっても過言ではありません。
こうした状況のなか、人事部門と経営層は一体となり、戦略人事に取り組むことで自社の人材の能力を最大化することが求められるのです。今後、人事部門が経営に果たす役割と責任は、ますます大きくなっていくでしょう。