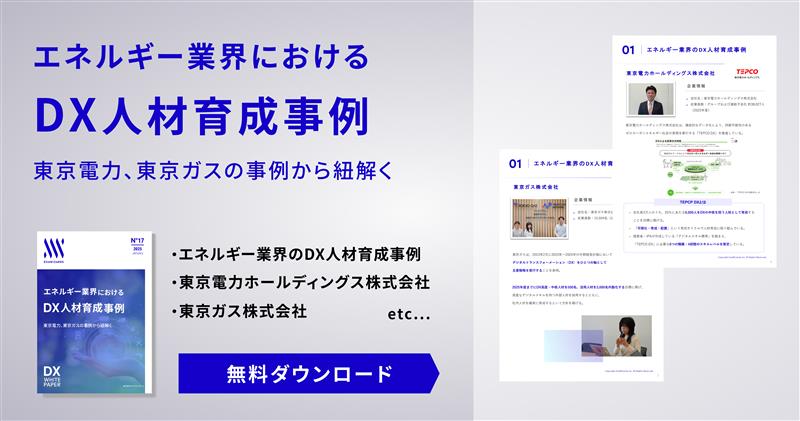近年、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が電力業界でも頻繁に聞かれるようになりました。DXとは単にITツールを導入することではなく、データとデジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセス、組織文化そのものを変革し、競争優位を確立することと経済産業省は定義しています。
従来のIT化(デジタイゼーション)が業務のデジタル化に留まるのに対し、DXは企業全体の構造変革を意味します。実際、経産省の調査では約9割以上の企業がDXに本格的に取り組めていない現状も明らかになりました。
つまり多くの大企業にとって、DXの共通認識や基礎知識が十分浸透しておらず、「何から手を付ければよいのか分からない」という声も少なくありません。
この記事では、電力業界の大企業を対象に、DXの基礎と共通認識を整理しつつ、電力業界特有の課題とDX推進の必要性を解説します。さらに、人材育成や組織改革の重要性に触れ、日本の大企業におけるDX成功事例を紹介しながら、DX導入促進への具体的アプローチを考察します。
<この記事の要約>
電力DXとは「再エネ普及・顧客ニーズ対応・運用効率化を支えるデジタル変革」
IoT・AI・クラウドを活用し、需給予測・スマートメーター・設備保守を高度化。再生可能エネルギー拡大と顧客サービス向上を両立する取り組みになる。
直面する課題は「規制・既存インフラ・サイバーリスク」になる
厳格な規制対応や老朽化設備との連携、サイバー攻撃のリスク管理が課題に。異業種技術導入や組織体制整備の必要性も高まっている。
成功の鍵は「戦略人材育成と協業・実証・改善の推進体制」になる
経営視点でDX戦略を策定し、人材育成と異業種協業を通じた実証実験を重ねる。現場主体の改善体制と柔軟な組織設計が成果の要となる。
電力業界でDXが急務となる背景:「5つのD」
電力業界は今、大きな環境変化の渦中にあります。その象徴が「5つのD」と呼ばれるキーワードです。これは電力ビジネスを取り巻く以下の5つの英単語の頭文字Dを指します。
- Deregulation(規制緩和):電力自由化に伴う競争環境の変化
- Decentralization(分散化):再生可能エネルギーの導入拡大による分散電源の増加
- Decarbonization(脱炭素化):気候変動対策としてCO2排出削減・再生エネシフトの加速
- Depopulation(人口減少):少子高齢化による需要構造の変化と労働力不足
- Digitalization(デジタル化):デジタル技術の進展と産業への浸透
この「5つのD」によって、電力業界は歴史的な大変革期を迎えています。これらのキーワードは主に外部環境の変化を示していますが、中でもDigitalization(デジタル化)は、事業者自身が積極的に取り組むことができ、かつ他のD(分散化・脱炭素・人口減少・規制緩和)とも密接に関連する横断的な要素と言えるでしょう。
つまり、デジタル技術を積極的に活用して自社を変革(DX)することは、他の環境変化への適応を加速する有力な手段となります。こうした背景から、電力業界においてDX推進は待ったなしの経営課題と言えるでしょう。
電力業界のDX現状と直面する課題
電力業界でDXが注目される一方、その導入推進には様々な課題も存在します。まず、業界全体の現状と代表的な課題を整理します。
- 人材不足・技術継承の問題
- 電力自由化による競争激化と新たなニーズ
- 脱炭素への対応と電力供給の安定化
- レガシーシステムと企業文化の壁
- DX推進における人材とデータ利活用の課題
1. 人材不足・技術継承の問題
日本は超高齢化に伴う人口減少局面にあり、多くの業界で人手不足が深刻です。電力業界も例外ではなく、送配電網の保守・工事など特殊技能を要する分野で後継者不足が顕在化しています。
特に大型送電線の建設や設備メンテナンスの現場ではベテラン技術者の高齢化が進み、技能伝承や人材確保が急務です。この課題に対し、業務の自動化やAI活用による省力化で労働生産性を上げ、人手不足を補う取り組みが求められています。DXにより現場作業を効率化し、熟練者の知見をデジタル技術で継承することが重要です。
2. 電力自由化による競争激化と新たなニーズ
2016年の電力小売全面自由化以降、従来は地域独占だった電力事業に多くの新規参入があり、大手電力会社同士の競争も激化しました。
電気を安定的に供給できること自体はもはや当たり前であり、各社はそれ以上の付加価値サービスを提供しなければ生き残れない時代になっています。具体的には、再生エネ由来の地産地消エネルギーサービスや、省エネ支援、家庭向けの新料金プランや見守りサービスなど、「電気+α」の新サービス創出が必要です。
DXによって顧客データを分析した新サービス開発や、業務の効率化によるコスト競争力の強化が不可欠です。また、需給バランスをリアルタイムに調整するためのデジタル技術導入(需給予測システムやデジタルグリッド技術など)も課題となっています。
3. 脱炭素への対応と電力供給の安定化
気候変動対策として日本政府も「2050年カーボンニュートラル」を掲げ、電力セクターでも再生可能エネルギー比率の拡大が進んでいます。太陽光や風力といった再エネはCO2を排出しない一方で、出力が天候に左右され供給が不安定という性質があります。
そのため、再エネ大量導入時代には需要と供給のバランスを取る「調整力」の確保が極めて重要です。つまり、蓄電池や需要側調整、他地域との融通などを駆使し、電力系統全体を安定化させる仕組みが必要になります。
これは国内だけでなく世界的にも大きな課題であり、AIによる需給予測・制御やデジタルツインによる系統シミュレーションなどのDX活用が求められています。
4. レガシーシステムと企業文化の壁
大企業ほど既存の基幹システムや業務プロセスが長年使われてきたもの(いわゆるレガシーシステム)に依存しがちで、DX推進の足かせになる場合があります。実際、2018年の経産省DXレポートでは古く複雑化した基幹システムの刷新の遅れがDXの障害になると指摘されました。
また、組織の縦割り構造や「失敗を許容しにくい企業文化」も、新しいデジタル施策の導入を阻む要因です。経産省は「DX=レガシーシステムの最新化」ではなく、「DX=社会環境に適応する企業文化への刷新」であると強調しています。
5. DX推進における人材とデータ利活用の課題
DXを進める上で人材と組織の課題も見逃せません。PwC Japanの2024年調査によれば、日本企業が感じているDX推進上の課題のトップは「人材育成・カルチャー変革」であり、次いで「データドリブン経営(データ利活用の促進)」「DX原資の確保(予算確保)」が挙げられています。
特に電力業界ではIT人材やデータサイエンティストが他業界に比べ不足しがちで、社内のデジタル人材の育成と採用が大きな課題です。また、膨大な設備データや需給データを十分に活用できていない企業も多く、データ基盤の整備や分析人材の育成が遅れています。DXを成功させるには、人とデータという二つの資源を最大限に活用できる体制づくりが不可欠です。
以上のように、電力業界のDX推進には内外で様々な壁がありますが、これらの課題こそがDXによって解決すべきテーマでもあります。次章では、こうした課題を乗り越えDX導入を成功させるための具体的アプローチを探ります。
データドリブン経営とは何なのかを知りたい方は、「【DXで再注目】データドリブン経営で意思決定のスピードアップ|課題や事例も紹介」もご覧ください。
DX導入を成功させるアプローチ
電力業界の大企業がDXを導入・推進するにあたり、どのような戦略やステップが必要になるでしょうか。ここでは、DX成功のためのアプローチを具体的に解説します。
- 経営トップによる明確なビジョンとコミットメント
- 専門部署・プロジェクトの設置と全社横断の推進体制
- 小さく始めてスケールさせる:PoCとアジャイル導入
- 最新テクノロジーの積極活用と基盤整備
- データドリブン経営への転換
- 顧客志向のサービス開発とビジネスモデル革新
1. 経営トップによる明確なビジョンとコミットメント
DXは企業変革プロジェクトであり、経営陣のリーダーシップが不可欠です。まず経営トップがDXの意義を正しく理解し、自社の経営戦略と結び付けた明確なビジョンを示すことが重要です。
「何のためにDXを行うのか(例:新たな収益源の創出、顧客サービス向上、業務効率化など)」を明確に定義し、全社に共有します。
東京電力では福島第一原発事故後の経営危機を背景に、DXの目的を「稼ぐ力の創造」と定めてグループ全体でDXに着手しました。
このようにトップが旗を振り、DX推進を中期経営計画などに位置付けることで、社内の共通認識と推進力が生まれます。
2. 専門部署・プロジェクトの設置と全社横断の推進体制
DXを効果的に進めるには、従来の縦割り組織を超えた専任チームやプロジェクト組織を設置することが有効です。
東京電力では「DXプロジェクト推進室」という専門部署を立ち上げ、デジタル化と業務プロセス改革の中核組織としました。このような専門部署やChief Digital Officer(CDO)の任命によって、社内のDX施策を統括し迅速に意思決定できる体制を築きます。
また各事業部門にもDX推進担当者や委員会を配置し、現場レベルでのデジタル施策を推進します。関西電力では2018年に社内にDX戦略委員会を立ち上げるとともに、各部門にもDX推進体制を構築しました。
さらにアクセンチュアとの合弁でデジタル専門会社「K4 Digital」を設立し、PoC(概念実証)など技術支援を行う体制を整えています。このように社内外のリソースを結集した推進体制を構築することが、DXをスピーディーに進めるポイントです。
3. 小さく始めてスケールさせる:PoCとアジャイル導入
DXは、一朝一夕に全業務を変革することは困難です。まずは小規模なプロジェクト(PoC)から始め、効果を検証しながら段階的にスケールアップするアプローチが有効です。例えば設備点検業務の一部にドローンやAI画像解析を試験導入してみる、需要予測に機械学習モデルを試すといった限定的な範囲でデジタル技術を実証します。
成果が確認できれば全社展開し、他分野にも横展開することでDXの恩恵を徐々に広げます。この際、アジャイル型の開発・導入手法を取り入れ、現場のフィードバックを素早く反映して改善を重ねることも重要です。
関西電力グループのK4 Digitalは、各種PoCを高速に回し、成功したものを事業現場へ実装する役割を担っています。
「スモールスタート&ナレッジ共有」で成功体験を積み重ね、DXへの社内理解を深めることで、大規模な変革への抵抗感を下げることが可能です。
4. 最新テクノロジーの積極活用と基盤整備
DX推進においては、個別技術の導入にとどまらず、業務課題に対してどのようにテクノロジーを紐付け、基盤を整備していくかが重要です。電力業界では、需給調整・電力市場との取引・再エネ活用の高度化など、複雑な運用課題に対応するため、AI・IoT・データ利活用の実装が加速しています。
たとえば、関西電力グループの分散エネルギーリソース運用事業を担うE-Flowでは、当社と連携し、AIによる電力市場での取引最適化に取り組んでいます。E-Flowは系統用蓄電池をはじめとする多様な分散エネルギーリソースを一元管理し、日々の市場入札や需給計画をAIで最適化。需給予測・電力価格・稼働条件などのビッグデータをもとに、複数市場における戦略的な入札計画を自動で立案しています。
参照:エクサウィザーズ「エクサウィザーズ、関西電力グループの 系統用蓄電池における運用事業でAIモデルが本格稼働〜分散した蓄電池の有効利用で、需給や価格を基にAIが複数の電力市場との取引を最適化~」
この取り組みにより、蓄電池保有顧客の運用収益向上や電力品質の安定化、さらには再生可能エネルギーの有効活用による脱炭素貢献が期待されており、電力業界におけるAI活用の先進事例となっています。
こうした高度な活用を支えるのが、堅牢で柔軟なIT・データ基盤です。エッジやクラウドを含むアーキテクチャの最適化、リアルタイムデータを取り扱うIoTプラットフォームの構築、セキュリティガバナンスの確立など、先端技術の効果を最大化するためには土台づくりも並行して進める必要があります。技術導入を単なる流行に終わらせず、事業構造の変革や社会課題の解決にどう結びつけるか。その視点が、DX成功の鍵を握ります。
5. データドリブン経営への転換
DX成功企業に共通するのが、データに基づいて意思決定する企業文化への転換です。電力会社はスマートメーターや発電設備から膨大なデータを日々得ていますが、これを活用してサービス改善や効率向上につなげることが重要になります。
例えば、
- 需要パターンの分析による需給計画の最適化
- 設備センサーデータによる故障予兆検知
- 顧客データ分析によるプラン提案
などが考えられます。
経営層から現場までデータに基づき判断する習慣を根付かせるために、KPIの可視化ダッシュボードを導入したり、データ分析の専門組織(データアナリティクス部門)を設置する企業も増えています。また、社内データだけでなく外部データや他企業とのデータ連携も視野に入れ、新たな価値創出につなげる発想も求められます。
データを戦略的資産と位置づけ、意思決定プロセスやビジネスモデルを「経験と勘」から「データに基づく科学的アプローチ」へとシフトさせることがDX推進の肝となります。
6. 顧客志向のサービス開発とビジネスモデル革新
DX導入のゴールは単に内部効率を上げることではなく、新たな価値の創出にあります。
電力会社で言えば、従来の発電・送配電・小売というバリューチェーンの枠を超えた新規事業やサービスモデルへの挑戦がDXの醍醐味です。顧客の潜在ニーズに応えるサービス開発には、デザイン思考など顧客志向のアプローチを取り入れ、異業種やスタートアップとの協業によるオープンイノベーションも有効でしょう。
また、エネルギーリソースを集約して需給調整サービスを提供するアグリゲーションビジネスや、地域の再エネと蓄電池を統合したマイクログリッド事業など、DXによって生まれる新しいビジネスモデルの可能性が広がっています。
自社の強み×デジタル技術で何ができるかを再定義し、「電力会社」の枠にとらわれない価値提供を模索することがDX成功への道と言えます。
以上のようなアプローチを総合的に推進することで、DX導入は現実の成果につながっていきます。次章では、実際にこれらの取り組みを進めて成功を収めている日本の大企業の事例を見てみましょう。
東京電力、東京ガスの事例から紐解くから学ぶ、エネルギー業界におけるDX人材育成のポイント
エネルギー業界においてもDXを推進する企業は年々増えつつあります。
DXを進めるうえでの課題 、またエネルギー業界におけるDX人材はどのように育成すべきなのでしょうか。
東京電力や東京ガスの取り組み事例から、業界ならではのDX推進のポイントやノウハウをまとめた資料をご用意しました。
ぜひ無料のお役立ち資料からご確認ください。
\こんな方におすすめの資料です/
- エネルギー業界においてDX人材育成を推進していく際のポイントを押さえたい
- エネルギー業界の実際のDX人材育成事例を参考にしたい
- 東京電力、東京ガスのDX人材戦略を参考にしたい
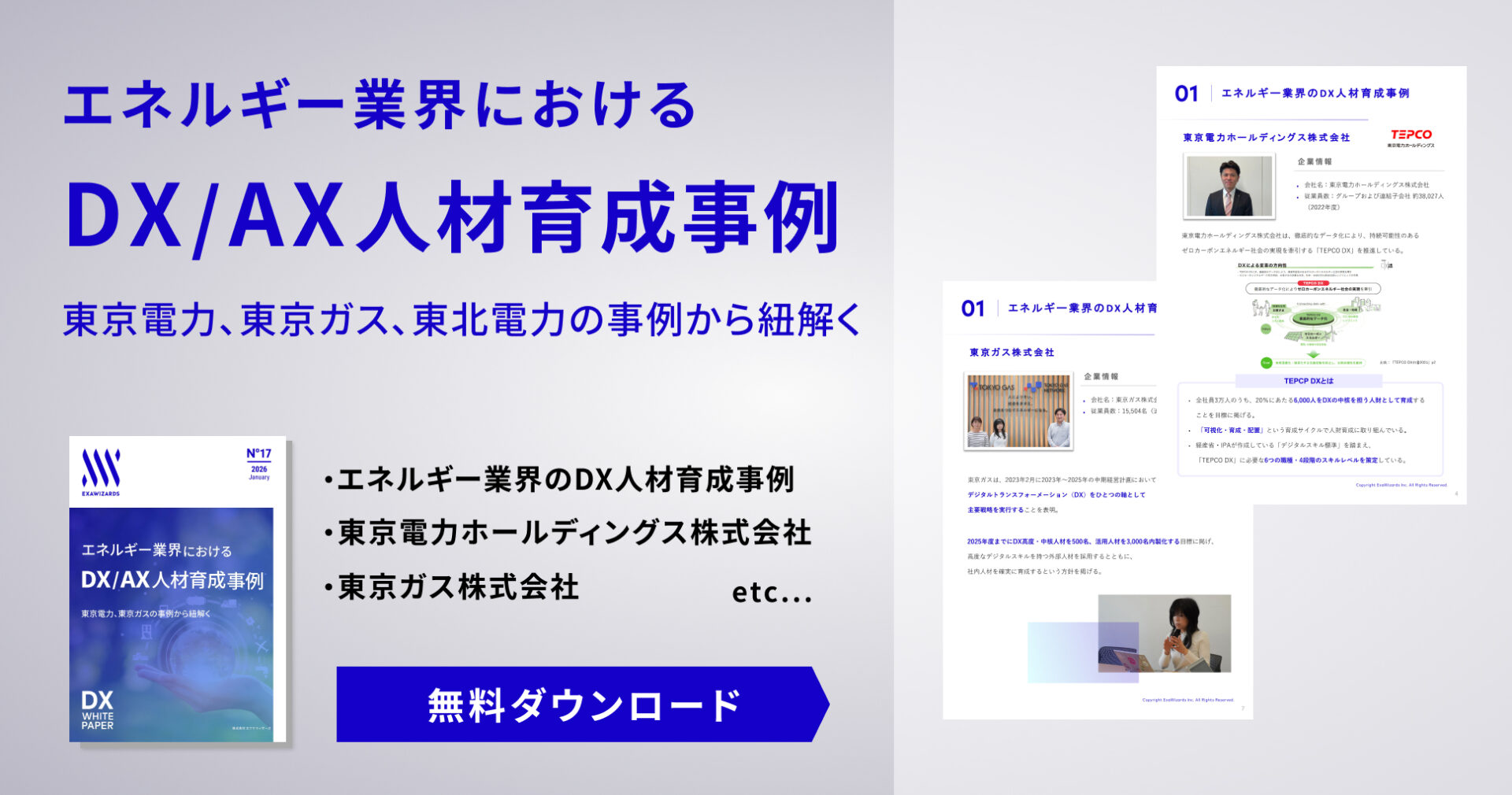
電力業界におけるDX成功事例
ここでは、電力業界の大手企業によるDXの成功事例を2つ紹介します。それぞれ目的やアプローチは異なりますが、DX推進のヒントとなるポイントを探ってみましょう。
- 事例1:東京電力ホールディングス – 「稼ぐ力」創造に向けたDX改革
- 事例2:関西電力送配電株式会社 – 安定供給とコスト削減のためのDX推進
- その他の大型企業におけるDXの動き
事例1:東京電力ホールディングス – 「稼ぐ力」創造に向けたDX改革
国内最大規模の電力会社である東京電力ホールディングス(東電)は、福島第一原発事故の賠償責任や電力自由化による収益悪化の危機感から、大胆なDX改革に乗り出しました。東電グループのDXは「稼ぐ力の創造」が最重要目的と位置付けられています。
具体的な施策として、
- グループ横断の「DXプロジェクト推進室」を発足
- 発電所や変電所の設備点検にIoTセンサーやAI画像診断を導入
- 電力データを活用したクラウドサービス事業への参入
などが進行中です。
東電の例は、明確な経営課題(収益改革)にDXを紐付け、専門組織でトップダウン推進することで、大企業でもDXを実行に移せることを示しています。
参照:東京電力「DXが実現する経営革新」
事例2:関西電力送配電株式会社 – 安定供給とコスト削減のためのDX推進
関西電力送配電株式会社(関西電力の送配電部門の分社化企業)は、電力自由化後の新たな競争環境に対応するため、低コストかつ安定的な電力供給の実現を目指してDXを推進しました。
具体策として、
- RPAの全社導入
- 設備点検の報告や社内稟議など各種手続きのデジタル化
- >ペーパーレス化と業務標準化
などを進め、現場の事務負担を削減するとともに、ヒューマンエラー防止や処理スピード向上といった効果を上げるなど、DXの成果を着実に上げています。
関西電力送配電のケースは、既存業務の効率化という身近な領域からDXを開始し、着実に成果を出しながら改革を深化させている好例と言えます。
参照:関西電力「関西電力グループのDXの取組みについて」
その他の大型企業におけるDXの動き
電力業界以外でも、日本の伝統的な大企業がDXで成果を上げつつあります。
製造業の日立製作所は老朽化インフラの遠隔監視サービスやIoTプラットフォーム「Lumada」を展開し、ハードからサービスへのビジネスモデル転換を遂げています。
また、自動車業界のトヨタ自動車はコネクテッドカーのデータを活用したモビリティサービスや、生産現場のスマート工場化などDX戦略を加速させています。
エネルギー業界ではENEOSホールディングス(旧JXTGエネルギー)が製油所のAI最適操業やモビリティ事業へのデジタル投資を進めています。
これらに共通するのは、デジタル技術を用いて自社の強みを活かしつつ、新たなサービス領域を開拓している点です。これらの事例から学び、電力業界のDX戦略に落とし込むことでさらなる成長機会を掴むことができるでしょう。
大型企業以外に、自治体や中小企業でもDXを導入し、効果を上げているところが増加しています。「【2024年最新版】DX事例集|国内外・自治体や中小企業まで自社に合ったDXの成功事例を見つけよう」で紹介していますので、参考にしてください。
人材育成と組織改革の視点:DXを支える「人」と「組織」
DX導入を真に軌道に乗せ定着させるためには、「人」と「組織」の変革が避けて通れません。最後に、人材育成と組織改革の重要性について考察します。
- DX人材の育成と確保
- 組織風土・カルチャーの改革
- 外部パートナーとの連携
DX人材の育成と確保
デジタル技術を使いこなしビジネスに活用できる人材(いわゆるDX人材)は、今や企業にとって最も重要な経営資源の一つです。しかし電力業界ではIT系の専門人材は限られており、社内の人材育成と社外からの獲得を計画的に進める必要があります。
具体的には、社員に対するデータサイエンスやAI、IoTに関する研修プログラムを設けてリスキリング(学び直し)を推進したり、社内公募でデジタルプロジェクトに参加する機会を増やすといった施策が考えられます。
関西電力の合弁会社K4 Digitalでは、グループ各社から集めたメンバーに対し年間の定量的スキル目標(スキルスコア)を設定し、人材育成を図っているとのことです。
また、中途採用や他業界との人材交流によって即戦力のデジタル人材を確保することも有効でしょう。特にデータアナリストやAIエンジニアなど高度IT人材は競争も激しいため、魅力ある職場環境(キャリアパスや待遇、やりがい)を用意して人材を惹きつける戦略が求められます。
DX人材の育成には、従業員のレベルを可視化したスキルマップの活用がおすすめです。「DX人材のスキルマップの作り方~スキルと素養を可視化し効率的な育成を~」で解説していますので、参考にしてください。
DX人材育成における、ROIの考え方・ポイントを大解剖
DX投資、人材育成は目的や投資対効果の考え方が異なります。
では、DX人材の育成に取り組む上でROIとどのように向き合うのが適切なのでしょうか。
本資料は、DX推進担当者向けに、DX人材育成を推進する上で重要な考え方3つをお伝えします。
DX人材育成の育成計画や目標を策定する際の参考としてお役立ていただけますと幸いです。
\こんな方におすすめの資料です/
- 人材育成におけるROIとの向き合い方がわからない
- 役員陣に対して、費用対効果の説明がうまくできない

組織風土・カルチャーの改革
DXを進める上で、人材のスキル以上に重要なのが組織のマインドセットです。従来の電力会社はどうしても規制業種ゆえの慎重な企業文化が根付いており、新しい挑戦への抵抗感があるかもしれません。DXを成功させる企業は例外なく「失敗から学び迅速に改善する」文化を育んでいます。
現場からアイデアを提案しやすい雰囲気作りや、チャレンジした社員を評価する制度づくりが必要です。また部門横断のコラボレーションを促進するために、組織のサイロ(縦割り)を取り払いプロジェクト横断型のチーム編成を常態化することも有効です。
関西電力ではDX人材戦略として、社員を「高度DX人材」「各部門のDX推進者」「全社員」の三層に分類し、それぞれに求められるデジタルスキルとマインドを定義して展開しています。
全社員がデジタルリテラシーを持ちつつ、要となる部門人材が牽引し、専門人材が高度技術をリードするという体制です。このように組織全体でデジタル時代に適応する人材像を描き、人材登用・配置や評価制度を見直すことが大切です。
外部パートナーとの連携
人材育成の延長線上で、社外の知見を積極的に取り入れる姿勢も欠かせません。DXが進んだ他企業との交流や、大学・研究機関との共同研究、ベンチャー企業との提携などを通じて、社内に新たな刺激と知識を取り込みます。前述の関西電力のケースでは、アクセンチュアとのジョイントベンチャー設立がその一例でした。
外部との協働により、自前主義では得られない高度なデジタル人材や最新ノウハウを活用でき、社内人材への良い刺激にもなります。電力業界はこれまで他業界に比べクローズドな側面がありましたが、DX時代にはオープンイノベーションが不可欠です。「社内の人材×社外の知見」で相乗効果を生み出す体制を築きましょう。
まとめ
電力業界の大企業にとって、DXは選択肢ではなく必須の経営課題です。技術革新や市場環境の激変に対応し、競争力を持続するには、単なるIT導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化の変革が欠かせません。
本記事で見てきたように、電力業界は「5つのD」に象徴される構造変化の只中にあり、DXによる対応が急務となっています。DXの本質は単なるIT導入ではなく、ビジネスモデルや組織文化の刷新によって競争力を高めることにあります。
その鍵となるのが、人材育成や組織改革です。DX推進には継続的な学習と戦略のアップデートが不可欠であり、共通認識の醸成や小さな成功体験の積み重ねが重要です。DXをやり遂げた企業こそが、未来の電力インフラを担う存在となるでしょう。
以下の資料では、エネルギー業界でのDX事例をまとめているため、ぜひご確認ください。