
意外な部門でDX人材を発掘
圧倒的に足りない起業家人材は「塾」で育てる
株式会社三井住友銀行 専務執行役員
デジタル・ICT推進部管掌
株式会社エクサウィザーズ 取締役
※所属等は、2023年3月の取材当時のものです。
デジタルを活用したビジネス変革に向けて、強力なリーダーシップを発揮したことが評価され、「Japan CDO of The Year」を受賞した、出光興産のCDO・CIO三枝幸夫氏。三井住友フィナンシャルグループのCDIO谷崎勝教氏。
前編に続き、後編では、デジタルの素養を持つアントレプレナー人材の育成方法や組織風土を変革するための取り組み、今まさに変革に挑戦しているCDOへのメッセージなどを伺いました。

DX人材を揃えるだけではダメ。アントレプレナー型の人材が圧倒的に足りていない
大植:お二人にはエクサウィザーズが提供するDX人材発掘・育成サービス「exaBase DXアセスメント&ラーニング」のアセスメントを受けていただきました。DX人材に必要なスキル・素養を定量化できるものですが、お二人ともに、新規事業や新規プロダクトを開発する能力「プロダクトマネジメント」と、DX施策を現場に導入してその反応を見てブラッシュアップしていく能力「実験力」の項目が満点でした。こうした素養はどのようにして身につけられたとお考えになりますか?
三枝氏:私の場合は、何でも新しいことに挑戦してみたくなる性格と、それを何とか社業にフィットさせる経験則があるからでしょうか(笑)

当社では、サービスを実際に利用していますが、社員のアセスメントの社員の結果も見ていると、意外な部門にDXの素養やスキルを持っている社員がいること分かるなど、いろいろな発見がある面白いツールだと思います。
谷崎氏:「プロダクトマネジメント力」も「実験力」も、デジタルを使って業務や会社を変えていくリーダーには欠かせない力なので、試行錯誤の中で培ってきた力なのではないかと思います。
こういったアセスメントで定点観測していけば、メンバーのスキルの変化を定量的にも見られて面白そうです。これから始まる人的資本開示の指標としても、意味が出てくるかもしれませんね。例えば、タレントが揃っている会社であることを統計的な数字として開示したら、採用的な観点でそれに惹きつけられる人も出てくるでしょう。
ただ、タレントが揃っているからといって、どんどん新しい事業やサービスが生まれるわけではありません。どういうサービスをお客さまに届けたいのかプランニングをして、サービスをローンチまで持っていって、それを事業として継続できるような、アントレプレナー型の人材も必要で、我々もこうした人材の層をどんどん厚くしていかなければいけないと思っています。

カルチャーのバトルを生き残れ。意識の変革には長い時間が必要
大植:こうしたアントレプレナー型の人材を育成するために、どのような取り組みをされていますか?
三枝氏:我々は中期経営計画で、全国6000カ所以上のサービスステーションを地域課題解決のサービスハブに進化させる「スマートよろずや」構想を掲げています。この名前にちなんで、「スマートよろずやデザイン塾」という教育プログラムを立ち上げ、デジタルの素養を持つ、社内アントレプレナーを育てる取り組みを行ってきました。この塾では、アントレプレナーシップの考え方やデザインシンキングなどを学びながら、ビジネスモデルを立ち上げ、PoCまでできることをゴールとしました。
この塾で学んだことは、必ず今の部署の仕事にも生きると思っていますので、こういった取り組みを地道に継続していきたいですね。
谷崎氏:我々は最初の方でも話した「社長製造業」を通して、社内起業家を育てようとしています。良い事業アイデアを持ってきた人を、社長に抜擢してしまうのです。社長になれば、成長戦略、技術戦略、人材戦略などを真剣に考えざるをえないですよね。
その中でうまく成功する事例が出れば、その下にも若い社員がいるので、そこでも人材が育ってくるはずです。そうした人材に、また、既存事業でも活躍してもらいます。
ただ、そこでもまた試練があって、カルチャーのバトルが発生すると思うのですよね。ここを、うまく生き残って、部署を改革していくことができれば、掛け算式に意識の変革したメンバーが増えていくでしょう。このジャーニーは、時間がかかるかもしれないですが、地道にやっていかなければならないと思っています。
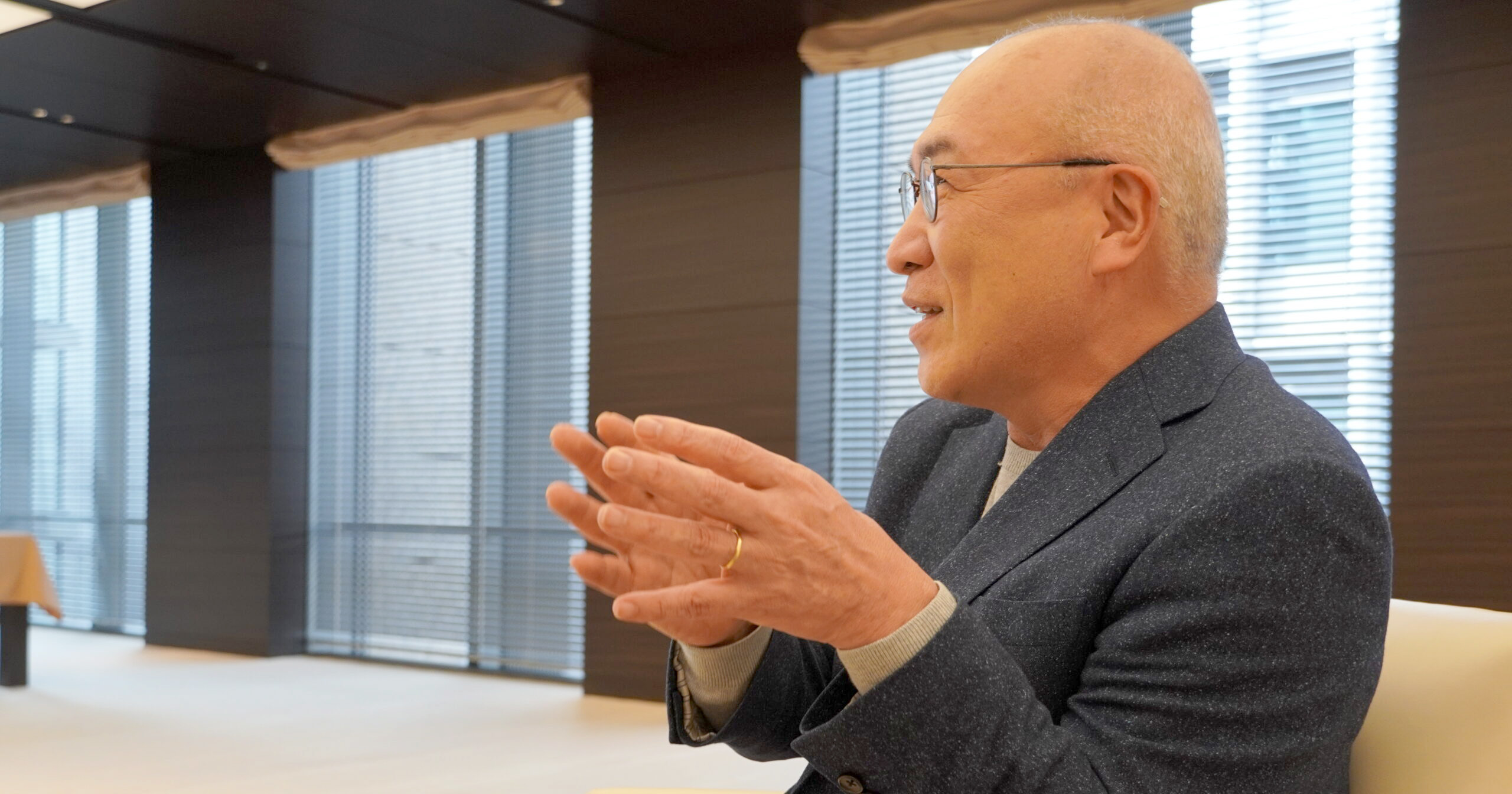
三枝氏:せっかく育てても、部署に戻すと、3カ月くらいで元に戻っている場合もあるんです。そうなったら、また半年ぐらい育成プログラムに参加してもらうといったこともあります。ジャーニーには長い時間が必要ですが、それがある枠を超えたとき、一気に組織が変わるのだと思います。
現場と経営の階層構造はデジタルで解消。外部企業ともワンチームで取り組む
大植:そういった若手社員のポテンシャルをいかに解放するかが、DXを成功に導く鍵となりますね。ただ、大企業の場合、役員に報告するまでに多重階層構造がある場合も多く、それがDXを遅らせる要因になっている印象があります。両社の場合は、どのようになっていますか。
谷崎氏:私も大企業における、社内を説得するためのエクスプラネーションコストっていうものは、すごく無駄が多いと思っています。ただ、これはデジタル技術が解き放してくれて、階層構造は徐々になくなってきていると感じています。なんなら、私を飛び越えて社長に直接報告してと言うこともあります。コロナ禍がこれを加速させましたよね。昔とはスピード感が全然違ってきているので、これからまた面白くなってくると思います。
三枝氏:デジタル化は情報の民主化だと思っています。リアルタイムに色んなビジネスがデジタルで進んでくれば、一番現場を知っているのは最前線の人です。そして、経営層は、全ての現場の情報を集めて俯瞰して意思決定をする役割を担います。デジタル化が進むと、経営と現場だけでいいという世界観になっていくはずです。
大植:では、我々のような外部企業との付き合い方として、何か意識されていることはあるでしょうか?
三枝氏:これまでのように、発注者と受注者の間柄で仕様書通りに作ってもらう、というような関係ではなくなってきています。デジタルはビジネスのメインストリームになってきますので、切り離して語る時代ではありません。ビジネスの目的を達成するために、ワンチームでやってもらえるところと組みたいですね。
だからこそ、コアなビジネスの課題とテクノロジーの両方を理解して、つなげる人材が重要になってきます。その部分では、社内の人材を育てていきたいと考えています。
谷崎氏:自前主義がいい、オープンイノベーションで外部と組んだらいいなど、いろいろな議論があると思いますが、私はどちらでもいいと思っています。
自分達だけでできるのなら全部やればいいし、足りないのであれば、外部企業に助けてもらえばいい。一番大切なのは、お客さまにサービスを届けることで、そのための一番良い方法を考えていけばいいだけなのです。
自前のエンジニアを育成するのに、何年もかけていたら、どんなサービスも陳腐化してしまいますよね。我々が米シリコンバレーにデジタルイノベーションラボを設置しているのは、最先端のテクノロジーを持つ人と組んで、最短でサービスを開発したいという目的もあります。
顧客視点のサービス開発に取り組むことが、社会課題につながる。めげずに挑戦し続けることで変革を
大植:最近では、サスティナビリティにどう貢献するかも、ビジネスの課題として大きく注目されています。ここにもDXによる見える化が大きな役割を果たしますね。
三枝氏:我々は、石油を扱う会社として責任は大きいと考えています。2050年に向けて、カーボンニュートラル宣言も出しています。GHG(温室効果ガス)のスコープ1(直接排出量)やスコープ2(間接排出量)はもう当たり前の世界になりつつあるのですが、スコープ3(Scope1と2以外のサプライヤーによる間接的な排出量)のトレーサビリティも我々の責務だと思っています。
これこそ、デジタルのど真ん中なので、業界と連携して進めていかなければなりません。これは企業の課題というだけではなく、デジタルに関わる我々全員の課題とも言えるかもしれません。

谷崎氏:我々は金融機関ではありますが、GHGの排出量の見える化サービス「Sustana(サスタナ) 」を提供しています。今後は、中小企業も、GHGの排出量の数字を示して納入しなければならない時代になるでしょう。そうした企業が、GHG削減のために新たな投資が必要になった際、金融機関としてお手伝いができればと考えています。
大植:私たちの会社も含め、ここにいる3社は、社会課題の解決を主眼に置いたビジネスを展開しています。その想いをお聞かせいただけますか。
谷崎氏:顧客視点でサービスを作っていくこと、それはすなわち、社会の困りごとを改善していくことだと考えています。
我々が提供している、医療情報のデータポータビリティを確保するためのサービス「情報銀行」も、日本の膨大な医療費の削減や、個人のウェルビーイングの向上を目指したものです。スマートシティに対しても、具体的な社会実装ができないかいろいろ模索しているところです。
このように、さまざまな事業をやっていると、解決しなければいけない社会課題がたくさん見つかってきます。こうした課題に対し、他の企業とも手を携えながら、解決を目指していきたいですね。
三枝氏:我々は「iX+(イクタス)」というメディアサイトを運営しています。デジタルにまだあまり馴染みのない人向けに、デジタルによって身の回りがどれだけ便利にできるかを広めようと考えています。デジタル社会がより進むことで、我々の提供するデジタルサービスも盛り上がってきますよね。デジタル化の恩恵を多くの人に感じてもらうことで、社会がより便利になっていってほしいと思っています。
大植:最後に、今まさに、変革に挑戦しているCDOの皆さんに向けて、メッセージをお願いします。
三枝氏:空気を読まないことが重要だと思います。心のトレーニングが必要ですね。
谷崎氏:孤軍奮闘になると思いますが、それにめげないことが大切ですよね。めげそうなことはたくさん起きますから。それでもなお、挑戦し続けないと変革は実現できないと思います。

三枝氏:ちょっとテクニック論になってしまうのですが、変革をやるにしても、既存の仕事を少し楽にしてあげることからのスタートでもいいと思うのです。例えば、現場で困っている業務をデジタルで楽にしてあげるなどでいいのです。それとセットで、新しい変革にも参加してもらう。組織の継続性を考えても、重要な手法だと思います。
谷崎氏:そういう意味では、CDO経験者がCEOになってほしいと思います。変革の挑戦者が成功して、トップに立つ。三枝さんのようなCDO経験者がトップになる時代が来れば、日本企業は本当に変わっていくんじゃないかと思っています。
※所属等は、2023年3月の取材当時のものです。

