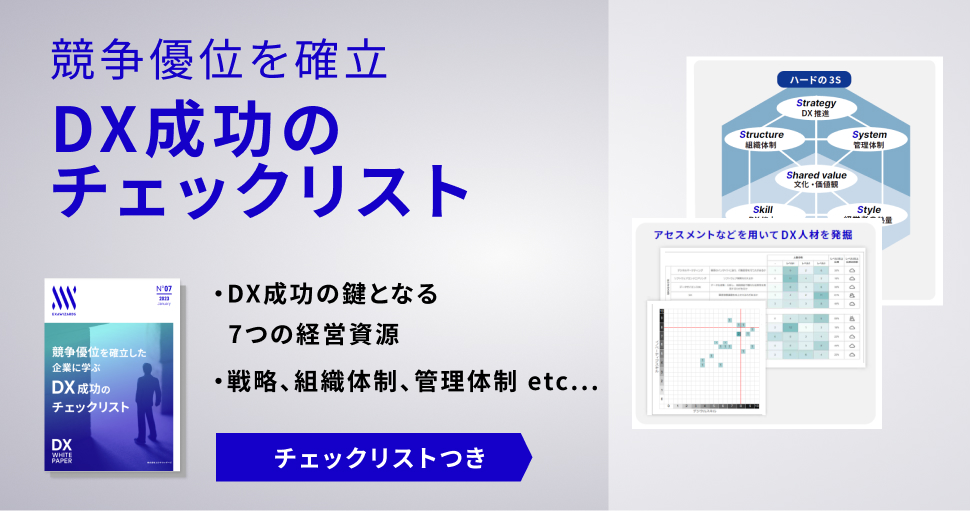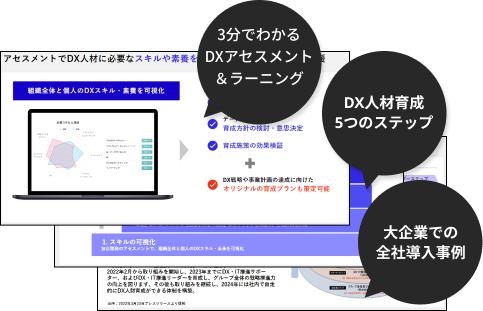DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進が求められている現代では、 日本のIT人材不足と基幹システムの老朽化、ビジョンや戦略の不明瞭化、予算不足、経営層のコミットが少ないことなどが問題となっています。
DXを実現するためには、これらの課題を解決しなければなりません。今回は、DXを推進する前に知っておきたい具体的な課題と、その課題に対する効果的な解決方法について解説していきます。
<この記事の要約>
DX課題とは「日本企業が直面する多層的なボトルネック」
IT人材不足やシステム老朽化、経営層の関与不足、文化醸成の遅れなどが複合的に影響し、DXの推進を阻む構造的な課題となって各企業に立ちはだかる。
背景には「経済損失リスクと組織変革の欠如」がある
基幹システム刷新の遅れにより「2025年の崖」リスクが拡大。DXが経営戦略に統合されず、担当部門任せになっている点が、構造的な停滞を招いている。
解決策は「経営のコミット&全社文化の構築」
トップの明確な意思表明と予算責任、教育体制の整備、社内人材の育成、IT投資の見直し、成果指標の導入など、全社的に一体化した改革が求められる。
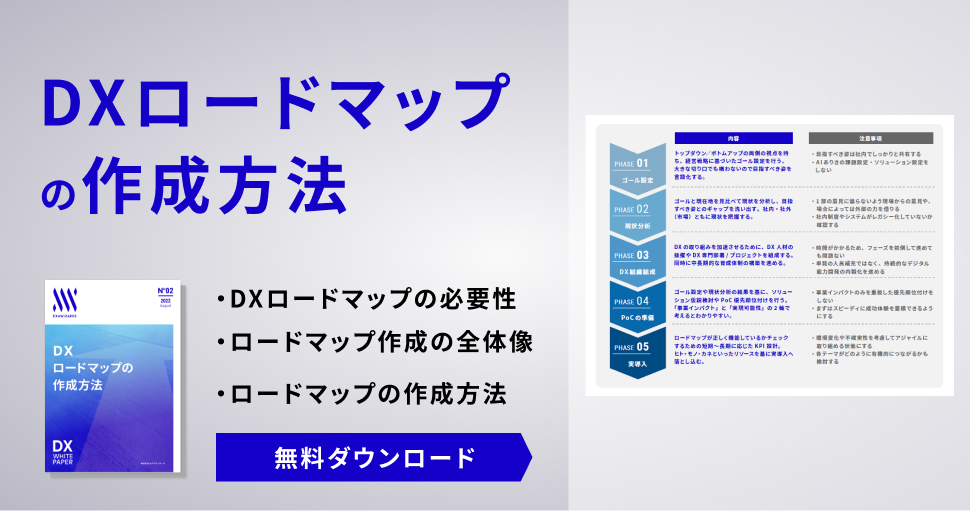
DXとは
DXとは、経済産業省により発行された「デジタル・ガバナンスコード3.0」によると、以下のように定義されています。
”企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズを基に、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。”
引用:『デジタル・ガバナンスコード3.0』経済産業省 2024年9月19日
つまり、DXとは単なるデジタル技術による業務効率化にとどまらず、あらゆる変革のきっかけとなり、新たな価値創造により競争優位性を生み出すものでなくてはなりません。
しかし、DXに取り組む中、多くの企業が課題に直面し、DX本来の目的を達成できていない現状があります。
DXの定義については、「DX(デジタルトランスフォーメーション)とは?推進に必要なポイントと最新事例をわかりやすく解説! 」でも解説していますので、合わせてご確認ください。
日本におけるDXの現状
それでは最新の資料から、日本におけるDXの現状を確認していきましょう。
DXの取り組み状況
DXにより競争優位性を生み出すためには、全社的な取り組みが不可欠です。各部門が独自に取り組んでいる状況では、それぞれの業務効率化のみが主眼となり、部分最適に終始しがちになるためです。
DXにおいて、全社戦略を打ち立て推進している企業の割合を見てみましょう。
【全社戦略に基づき、全社もしくは一部の部門でDXに取り組んでいる企業の割合】
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 45.3% | 54.2% | 59.4% | 58.4% |
参考:『DX動向2025 P2図表1-1』独立行政法人 情報処理推進機構 2025年6月26日
2021年度には50%を割り込んでいましたが、2023年度には6割近くの企業が何らかの全社戦略を打ち出し、DXを推進しています。日本全体で取り組みが進んでいるものの、2022年度の米国の水準68.1%には及ばない状況です。
DXの成果状況
全社戦略に基づきDXを推進している企業の内、どれくらいが成果を実感できているかの資料が以下です。
【全社戦略に基づきDXを推進し成果が出ている企業の割合】
| 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 |
|---|---|---|---|
| 49.5% | 58.0% | 64.3% | 57.8% |
参考:『DX動向2025 P2図表1-1』独立行政法人 情報処理推進機構 2025年6月26日
経年とともにDXの成果を実感する企業は増えており、2023年度においては64.3%にものぼります。「成果が出ていない」と回答した企業の割合も大きく減少しており、全社戦略に基づいたDX推進は、何らかの成果につながっていることが分かるでしょう。
日本のDXにおける課題
レガシーシステムの刷新が進まなければ、最大12兆円もの経済損失が発生するとした「2025年の崖問題」の提唱により、多くの企業が危機感を持ち、DXに取り組み始めました。
こうした流れの中、浮き彫りになった課題を整理していきましょう。
DXにおける失敗事例は、きっと参考になるはずです。「DXに失敗しないために、DXの失敗事例とその要因、対策を解説!」をぜひご一読ください。
経営の課題
DXは全社を巻き込んで長期的に取り組むべきものです。そのためには全社で同じ方向を向き、途中でぶれない強烈なコミットが必要になります。そのためには経営層が中心となって戦略やビジョン、ロードマップを策定し、現場が途中で諦めないように経営層がコミットする必要があります。
しかし、以下に挙げるような阻害要因がDX推進を阻む課題となっている現状があります。
- 経営層のDXに対する関心の低さ
- 変革に対する抵抗意識
- 消極的なデジタル投資
こうした課題は、経営層の積極的なリードがあれば、多くは克服できるものです。
ITに見識がある役員の割合が低い
DXの成果が出ていない企業は、やはりITに見識のある役員が不在、もしくは少ない傾向が見て取れます。
【ITに見識がある役員の割合(成果別)】
| 5割以 | 3割以上5割未満 | 3割未満 | いない | |
|---|---|---|---|---|
| 成果が出ている | 11.5% | 8.2% | 63.9% | 16.4% |
| 成果が出ていない | 4.5% | 4.5% | 55.5% | 35.5% |
参考:『DX動向2024 P7図表1-11』独立行政法人 情報処理推進機構 2024年6月27日
成果が出ていない企業では約35%が、ITに見識のある役員がいないと回答しています。また、3割以上いる企業では「成果が出ていない」割合も少ないようです。
やはり、DXの推進は経営層のリーダーシップによる主導が欠かせません。役員自身が率先して、ITへの見識を高めることが急務となるでしょう。
経営層・IT部門・業務部門の連携が十分でない
経営層のリードが弱ければ、DXに対する全社的な連携は強化されません。経営層・IT部門・業務部門の連携についての調査結果が以下の表です。
【経営層・IT部門・業務部門の協調】
| 日本企業 | 米国企業 | |
|---|---|---|
| 十分にできている | 5.9% | 31.9% |
| まあまあできている | 31.2% | 48.2% |
| どちらともいえない | 30.5% | 13.7% |
| あまりできていない | 20.5% | 2.3% |
| できていない | 11.3% | 3.9% |
参考:『DX白書2023 P17 図表1-15』独立行政法人情報処理推進機構 2023年3月16日
経営層・IT部門・業務部門の連携が「できている」とした企業は日本では4割にも満たない状況で、米国では8割以上と大きな隔たりがあります。
全社的な連携が進まないのは、CDO(最高デジタル責任者)が不在であることも要因の一つのようです。米国では6割以上の企業でCDOという役職が設置され、役員クラスの人材がDXの陣頭指揮を取っていることが伺えます。
対して日本は、DXの成果が出ている企業でも、CDOがいる企業は2割ほどしかありません。
参考:『DX動向2024 P7図表1-10』独立行政法人 情報処理推進機構 2024年6月27日
DX推進のための予算が確保できない
DXに関する予算が確保できないことも、大きな課題です。年度の予算内に継続してDXの予算が確保されている企業の割合は、2022年度で22.8%、2023年度でやや改善して36.5%となっていますが、依然として低い水準です。
大多数の企業は、年度ごとに申請して認可が下りたものについてのみ、予算が確保できるという状況です。DXの取り組みは継続性が不可欠であり、毎年一定の予算は必ず確保すべきでしょう。
やはり、予算確保の面でも経営層のDXに対する、さらなるコミットが求められるのです。
参考:『DX動向2024 P5図表1-6』独立行政法人 情報処理推進機構 2024年6月27日
競争優位を確立した企業にDX成功の秘訣を学ぼう!
DXを実施するにあたっては、単に既存業務の効率化をおこなうだけでなく、どのように競合優位性を確立するかという経営観点にもとづいた推進が必要です。
先行してDX推進を成功させた企業は何を取り組んだのか?
年間300件以上のDX推進プロジェクトを支援した実績から、事例やノウハウをまとめた資料をご用意しました。
推進成功企業を7つの経営資源(7S)で大解剖していますので、ぜひ無料のお役立ち資料からご確認ください。
\こんな方におすすめの資料です/
- 単なるAI導入やツール導入ではなく、ビジネスモデルを変革したい
- 経営の観点でDXを推進したい
人材の課題
日本企業でDXが進まない要因として、DX人材の確保が容易ではないことが挙げられます。
「DX動向2024」では、DX人材の質と量の側面から充足度を調査していますが、日本における確保状況はまだまだ厳しい状況です。
【DX人材の質・量の側面で充足していると答えた企業の割合】
| 量の確保 | 質の確保 | |
|---|---|---|
| 2023年度日本企業 | 4.6% | 3.8% |
| 2022年度米国企業 | 73.4% | 88.3% |
米国と比較し、致命的にDX人材の確保が進んでいない現状が浮き彫りになっています。
DXを推進する人材の中でも最も不足しているのが「ビジネスアーキテクト」という人材類型です。ビジネスアーキテクトは、DXの取り組みにおいて全体像をデザインし推進する役割を担います。
高度なIT知識だけでなく、マーケットや経営に関する広範な知識が必要であり、こうした人材の育成が急務となっているのです。
参考:『DX動向2024 P31図表3-1 3-2 3-4 』独立行政法人 情報処理推進機構 2024年6月27日
DX人材の不足と解決法については、「DX人材不足の要因から紐解く、DX人材を確保するための6つの対処法!」でも解説していますので、合わせてご確認ください。
システムの課題
「2025年の崖問題」の提唱により、レガシーシステムを刷新できないことによる危機感は、かなり浸透したことが伺えます。
レガシーシステムの刷新状況の経年変化を見てみましょう。
【レガシーシステムの状況】
| 2022年度 | 2023年度 | |
|---|---|---|
| レガシーシステムはない | 12.2% | 24.0% |
| 一部領域にのみレガシーシステムが残る | 28.2% | 34.0% |
| 半分程度がレガシーシステム | 19.2% | 13.8% |
| ほとんどがレガシーシステム | 22.0% | 15.0% |
参考:『DX動向2024 P26図表2-15 』独立行政法人 情報処理推進機構 2024年6月27日
2023年度では半数以上の企業において、レガシーシステムの刷新の目途が立っている状況が見て取れます。しかし、割合が減ってはいるものの、レガシーシステムの刷新が、まったく進んでいない企業も一定数存在することも確かです。
レガシーシステムの刷新が進まない原因として挙げられる主な課題は、以下の通りです。
- 経営者の理解不足
- 予算や納期確保のむつかしさ
- 現システムの操作性へのこだわりが払拭できない
- 既存システムの解析が困難
- 刷新による影響度が把握できない
- 刷新に向けたリソース確保が困難
こうした課題が複雑に絡み合い、システムの刷新を阻んでいる現状があります。根気強く紐解いていき、一つひとつ課題をクリアしていかなくてはなりません。
参考:『DX動向2024 P28図表2-17 』独立行政法人 情報処理推進機構 2024年6月27日
ユーザー企業とベンダー企業の関係の課題
現在のユーザー企業と販売会社であるベンダー企業が「相互依存関係」であることも、DXを推進する能力が育たない理由の一つとDXレポートでは言及されています。日本のユーザー企業はITをコストと捉える場合が多く、ITをベンダー企業に委託しているのが現状です。結果的に社内のIT対応能力は育たず、システムはブラックボックス化します。
ベンダー企業は基本的に労働量に対してサービス料金を決めているため、労働量が下がるような生産性を向上させるインセンティブが働かず新たな能力開発や技術開発投資がなされません。これにより最新の技術に対応できない構造ができてしまっています。これを本レポートでは「低位安定」の関係だとしています。ユーザー企業とベンダー企業の関係性を変えることは、一足飛びにはいけない大きな壁があるのです。
出典: 『DXレポート2.1』経済産業省 令和3年8月31日
社内のDXスキル育成の課題
上述した通り、DX推進には社内にDXスキルを持つ人材が必要です。しかし、現在の日本はDX人材の不足が浮き彫りになっています。ユーザー企業にITで何ができるか理解できている人材がいないことから、DXに関してはベンダー企業に任せきりになるという悪循環が起こっています。特に、企業内で人材確保が難しい中小企業ほど、社内のDXスキルが一向に育たないままになっています。
「文系社員」をDX人材に導く、リスキリングの取り組みとは?
企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)に取り組む中で、直面する課題の1つに「DX⼈材の不足」があります。
採用だけでなく、既存社員の育成、リスキリングに取り組む企業も少なくありません。
その中で、文系社員に対し、デジタルスキルやリテラシーをリスキリングしてもらうには、どのような取り組みをすべきなのでしょうか。
本資料では、DX推進に必要な⼈材の定義、具体的な育成プラン、リスキリングについて株式会社PeopleX 代表取締役CEO橘氏との議論の内容を紹介します。
\こんな方におすすめの資料です/
- DX人材育成の進め方のポイントを知りたい
- ビジネスアーキテクトの概要を知りたい
- 「文系社員」のリスキリングを検討している

DXの課題を解決するために
上述の通り、DXにはさまざまな課題があることが分かりました。では、DXの課題に対する具体的な解決策はどのようなものがあるのでしょうか。DXを推進していくためのポイントをいくつかご紹介します。
経営がDXにコミットする
DXを推進していくために、「DXでどのように新たな価値を生み出すか」「どのようなビジネスモデルを構築すべきか」について経営層が明確にビジョンを描き、ロードマップの策定と経営戦略を打ち出していく必要があります。そのため、DXのプロジェクトは、部門を横断した全社的なプロジェクトとなるでしょう。
トップが明確なDX戦略の方向性を示してリーダーシップを取れば、DXに対する社員の意思統一もスムーズになるはずです。
まずは、経営層がDXの必要性や重要性ついてより深く理解することが大切です。部下にプロジェクトを丸投げするのではなく、強いコミットメントを持って取り組んでいきましょう。
全社的にDXの雰囲気・文化を醸成する
DXは、社内のIT部門・情報システム部門のみが関係する話ではありません。特定の部門が単独で行うのではなく、各部署で連携を取ってDXの雰囲気や文化を醸成していくことが大切です。
まずは、デジタイゼーション(アナログで行ってきた業務をデジタル化)やデジタライゼーション(ワークフロー全体をデジタル化)などできることから始めましょう。デジタルで管理することによって、データがより活用しやすくなります。ただし、業務をデジタル化しただけで満足してしまっては、DXの目標であるビジネス変革が実現できないため、注意が必要です。
また、DX推進による既存システムの刷新は、現場サイドからの反発がある場合もあります。社内の方向性が一つに定まらないときこそ、DXを推し進めるために経営層から発信を強めることが重要です。その際、社内全部門が一丸となってDXに取り組めるような体制の整備や、DXについて考える時間を増やす仕組みづくりも合わせて行っていきましょう。
DX推進を成功させる、社内を動かす・うまく巻き込むコツとは?
組織的にDXを推進し、事業変革を進めるためには「社内をうまく巻き込んでいく」ことが重要となります。
しかし、思ったように社内の協力を得られず、DXが進まないと悩んでいる担当者は少なくないものです。
本資料では、「DX推進における社内巻き込みの重要性」、「巻き込みを成功させる3つのポイント」など、全社的なDX推進に必要となってくる「社内の巻き込み」にご紹介していますので、ぜひダウンロードしてお役立てください。
\こんな方におすすめの資料です/
- DX推進に他部署の協力が得られない
- 一部のDXではなく全社的なDXを推進したい
DX人材を育成する
「ITシステムを理解していた人材が退職してしまった」「ITシステムに関する業務を全てベンダー企業に任せている」などの理由から、社内でITシステムを理解できる人材が少ない企業もあるでしょう。DXは、自社の製品や内情に詳しい人が担う方が良いため、社内の人材の育成は必須だと考えておきましょう。
ITに詳しい社員に対して、スキルアップを推奨する制度・環境を用意し、プロからフィードバックを受けたり共にDXプロジェクトを推進したりすることで、短期集中的にDX人材を育てることが可能になります。
DX人材の育成には、アセスメント実施によるDXの素養を持つ人材の発掘と、対象者に向けた適切な教育が欠かせません。
exaBase DXアセスメント&ラーニングはその両方が実現するツールです。
社内のDX人材の発掘と育成までをサポートする「exaBase DXアセスメント&ラーニング」のサービス紹介や「DX人材育成の5つのステップ」「大企業での導入事例」を資料にまとめました。
\こんな方におすすめ/
- DX人材を社内から選抜・育成したい
- DX人材の育成計画や要件定義をしたい
- 業務に繋がる実務スキルを習得したい

DX人材の育成方法については、「DX人材育成の方法を大公開。DX人材育成5つのステップはスキルと素養の可視化から」で説明していますので、ぜひご一読ください。
攻めのIT投資を行う
IT投資には、「攻め」と「守り」の二つがあります。日本では守りのIT投資が多くなっていますが、守りのIT投資では業務効率化や生産性の向上を目指すためだけにコストを割くことになります。
しかし、攻めのIT投資はITによる新たなビジネスを生み出すだけでなく、ビジネスモデルの変革を目指すことを目的とした動きにコストをかけるという特徴があります。今の日本のような守りの投資のままではDXの実現は難しいため、攻めのIT投資を検討する必要があります。
DX評価指標を作成する
経済産業省は、日本の企業がDXにおいて実証的な取り組みがあるものの、ビジネス変革までは至っていないと訴えています。そこで、経済産業省はDXがどの程度推進しているのかを各企業が自己判断できる「DX推進指標」を作成しました。
この評価指標を利用すれば、DX推進の現状や課題について気づくことができます。その気づきから、改善案やDX推進計画を立てるとよいでしょう。
出典:『デジタル経営改革のための評価指標(「DX推進指標」)を取りまとめました』経済産業省 2019年7月31日
業界別・企業規模別のDX課題
DXの課題は企業規模や業界によって大きく異なります。
一般的な課題だけでなく、それぞれが抱える特有の課題を理解することが、より本質的なDX推進にとって重要です。
ここでは、特にDX推進に遅れが出ている企業規模・業界である中小企業、製造業・建設業、自治体・官公庁という三つの観点から、具体的な課題について詳しく解説します。
業界や規模の違う企業であっても共通する内容もございますので、ぜひご参照ください。
中小企業におけるDX推進の課題
中小企業のDX推進では、特に資金面での制約が大きく、IT投資に十分な予算を確保することが困難な状況が多いです。また人材確保の面でも、DXに精通した専門人材を採用する競争力が大企業に比べて劣る傾向があります。
資金不足の問題は深刻で、DXに必要なシステム導入費用、人材教育費、外部コンサルティング費用などが重い負担となります。中小企業の多くは年商に占めるIT投資の割合が低く、必要最小限のシステムのみを導入している状況です。この結果、旧態依然のシステムから脱却できずにいる企業が多数存在しているのです。
人材確保の困難さも中小企業特有の課題です。IT人材の需要が高まる中、給与水準や福利厚生の面で大企業に劣る中小企業は、優秀なDX人材を確保することが容易ではありません。
既存社員のリスキリングも重要ですが、研修時間の確保や教育体制の整備も大きな課題となっています。
参考:『「2025年の崖」が迫るも、レガシーシステムから「脱却できていない」31.6%。その理由とは!?』株式会社オロ
製造業・建設業におけるDX推進の課題
製造業と建設業は、現場作業が中心となる業界であり、デジタル化について多くの課題があります。製造業では工場の生産ライン、建設業では建設現場といった物理的な作業環境をデジタル化する必要があり、単純なオフィス業務のデジタル化とは異なる複雑さがあるのです。
現場作業のデジタル化において最も大きな課題は、既存の業務フローとの兼ね合いです。長年培われてきた現場のノウハウや作業手順をデジタル技術に置き換える際、作業効率が一時的に低下することがあります。
また、現場作業者の多くがデジタル技術に不慣れであることも、導入を困難にしている要因です。
既存システムとの連携も重要な課題です。製造業では生産管理システム、品質管理システム、在庫管理システムなど複数のシステムが稼働していることが多く、これらを合わせて運用するためには高度な技術的知識が必要です。
建設業でも、設計システム、施工管理システム、安全管理システムなどの連携が求められます。
自治体・官公庁におけるDX推進の課題
自治体や官公庁のDX推進で最も大きな制約は予算制約であり、年度予算制度の下で長期的なDX投資計画を立てることが困難な状況です。また、住民への説明責任も重く、費用対効果を明確に示すことが求められます。
職員のITスキル不足も深刻な課題です。自治体職員の多くは行政の専門知識は豊富ですが、IT技術に関する知識は限定的です。また、定期的な人事異動により、せっかく育成したIT人材が他部署に異動してしまうという問題もあります。
rakumo株式会社の調査「自治体のDX推進に関する実態調査」によると、自治体のDX推進担当105名にお勤めの自治体におけるDX推進の現状を自己評価すると、どの段階にあると感じるか聞いたところ、以下の結果になったとのことです。
- どちらかといえば遅れている:35.2%
- 非常に遅れている:12.4%
この結果からも、多くの自治体でDX推進が課題となっていると言えるでしょう。
参考:『【自治体のDX推進に関する実態調査】自治体のDX推進、約5割が遅れを自覚。人材やコスト面で課題』rakumo 株式会社
政府機関によるDX課題への取り組み支援
政府は日本のDX推進を加速させるため、各省庁で多くの支援制度を設けています。経済産業省、国土交通省、総務省がそれぞれの所管分野において展開している施策について、ここでは紹介していきます。
経済産業省のDX推進政策
経済産業省は日本のDX推進において中心的な役割を担っています。その中でも象徴的なのが、DX認定制度を通じて企業のDXへの取り組みを評価・認定している取り組みです。
DX認定制度は、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、「デジタルガバナンス・コード」の基本的事項に対応する企業を国が認定する制度で、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が制度事務局として運営しています。
この制度の特徴は、2024年12月から新基準に基づく運用を開始し、中小企業等での取得が約1.6倍と全認定事業者数の増加を牽引している点です。認定を受けた企業は、社会的信頼の向上、金融機関からの優遇融資、DX銘柄への応募資格獲得などのメリットを享受できます。
IT導入補助金やものづくり補助金も、経済産業省が行っている重要な支援制度です。IT導入補助金では、中小企業のITツール導入を支援し、業務効率化や売上向上を図っています。ものづくり補助金では、製造業を中心とした企業の設備投資や技術開発を支援し、DXを通じた競争力強化を促進しています。
参考:『DX認定制度概要 ~認定基準改訂及び申請のポイント~』経済産業省
参考:『産業界のデジタルトランスフォーメーション(DX)推進施策について』経済産業省
国土交通省のDX推進政策
国土交通省は、インフラ分野のDX推進において「i-Construction」政策を展開し、建設現場の生産性向上とデジタル技術の活用を積極的に推進しています。
2024年度からは「i-Construction 2.0」を打ち出し、建設現場のオートメーション化を目指した取り組みを推進し、少ない人数で安全かつ快適な環境で働く、生産性の高い建設現場の実現を目指しています。
この政策の中核となるのがBIM/CIM(Building/Construction Information Modeling/Management)の活用促進です。設計から施工、維持管理まで一貫したデジタル化を実現し、関係者間の情報共有の質を向上させています。
また、国土交通省では「インフラDX大賞」を実施し、インフラ分野のデジタルトランスフォーメーションにおける優れた取り組みを表彰しているのも大きな特徴です。これは従来の「i-Construction大賞」を発展させたもので、建設現場の生産性向上とデジタル技術の活用を目的としています。
参考:『i-Construction の推進』国土交通省
参考:『BIM/CIMの進め方について』国土交通省
総務省の自治体DX化支援と地域課題解決策
総務省は自治体DX推進の司令塔として「自治体デジタル・トランスフォーメーション(DX)推進計画」を策定し、自治体が重点的に取り組むべき事項・内容を具体化するとともに、関係省庁による支援策等をとりまとめています。
この推進計画では、情報システムの標準化・共通化、行政手続きのオンライン化、AI・RPAの利用推進など6つの重点取組事項が定められています。
直近令和7年3月には「自治体DX推進計画【第4.0版】」として最新の改定を行い、自治体の取組状況を踏まえた内容の充実を図っています。
また、デジタル田園都市国家構想による地域支援も重要な施策です。この構想は「心ゆたかな暮らし」(Well-Being)と「持続可能な環境・社会・経済」(Sustainability)を実現していく構想で、地方がそれぞれの特性に応じた発展を遂げることができるよう支援しています。
参考:『自治体DXの推進に向けた取組について』総務省
参考:『デジタル田園都市国家構想総合戦略関係施策について』内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局
まとめ
DXを推進するには、経営層が課題を明確化し、リーダーシップを発揮しなければなりません。経営層側から積極的に働きかけ、DX人材の採用や育成・研修などを行い、社内全体にDX戦略を醸成していきましょう。また、課題に直面した際は、プロなどの第3者の意見を参考にするのもおすすめです。